「新しいクラスで気になる子」5月の振り返りと支援のヒント
~不安や違和感を見逃さず、保育の質を高めるために~
4月から始まった新しいクラスも、1か月が経過。
少しずつ日常のリズムが整い、子どもたちの表情や行動にも“その子らしさ”が見えるようになってくる時期です。
一方で、「泣くことが多い」「関わりが少ない」「よく動きすぎる」など、“なんとなく気になる”子の姿が目に入るようになるのも5月。
本記事では、その“気になり”にどのように向き合えばよいか、保育士としての視点と対応のヒントを年齢別にお伝えします。
1. なぜ「気になる子」が見えてくるのか?
4月は新しい環境に適応するために、子どもも大人も“とにかく慣れる”ことで精一杯。
5月に入ると少し余裕が出てきて、子どもたちの行動や感情の揺れが見えやすくなってきます。
この時期は、「どう関わればよいか、まだつかめない」「何となく他の子と違う気がする」など、“小さな違和感”が保育士のアンテナに引っかかるときでもあります。
2. 5月は「気づきと振り返り」のタイミング
新年度の慌ただしさが落ち着く5月は、日々の保育の記録や観察をもとに、“その子らしさ”を捉え直す大事な時期です。
- 気になる行動が一時的な環境変化によるものなのか
- それとも継続的な関わりが必要なサインなのか
こうした視点で、記録を振り返ることで支援の方向性が見えてきます。
3. 年齢別|よくある“気になるサイン”と支援の視点
● 0歳児・1歳児
よくあるサイン:
- 食事・睡眠に強い拒否
- 保育者へのかかわりが極端に少ない or 固定されている
- 泣きが長引く/頻繁に泣く
支援のヒント:
- 安心基地(担当保育士)との関係づくりを重視
- 無理に集団へ入れず、「一対一の関係」を丁寧に積み上げる
- 身体面の不調(体調・アレルギーなど)も併せて確認
● 2歳児・3歳児
よくあるサイン:
- 友だちとの関わりがほとんど見られない
- 一人遊びに固執/場に入りづらい様子
- 指示を聞き取れていない/極端に反応が遅い
支援のヒント:
- 無理に「集団の中」へ入れようとせず、安心できる場所での遊びから
- 遊びを通した保育者の仲介で、関わりのきっかけをつくる
- 言葉の発達や感覚の特性にも目を向ける
● 4歳児・5歳児
よくあるサイン:
- 周囲とのトラブルが多い(叩く/無視/大声を出すなど)
- 空気を読めない/活動の流れについていけない
- 反抗・拒否が極端(やらない/逃げる/泣きわめく)
支援のヒント:
- ルールの理解や感情コントロールの力を丁寧に見極める
- 「できた体験」「見通しの持てる活動」を増やしていく
- 叱るよりも、「どうすればよかったか」を一緒に考える関わりを
4. 記録とチーム共有のポイント
「なんとなく」ではなく、客観的な観察と記録が大切です。
- いつ/どこで/誰と/どんな様子だったかを具体的に記録
- 同じ子について複数の保育者が記録を見比べる
- 担任だけで抱え込まず、主任・看護師・園長とも共有
共有によって、「見る視点」が増え、より的確な支援に繋がります。
5. 保護者対応で気をつけたいこと
気になることがあっても、すぐに保護者へ伝えるのは慎重に。
まずは信頼関係の構築を優先し、「困っていること・できるようになったこと」をセットで伝えるのがポイントです。
伝え方の例:
最近、活動中にお友だちの輪に入りにくそうな場面がありました。
でも、お絵描きのときにはとても集中していて、話しかけるとニコッと笑ってくれました。
引き続き様子を見ながら、関わりのきっかけをつくっていきますね。
6. まとめ|観察を“気づき”につなげる保育を
「気になる子」は、“育ちが遅れている子”ではなく、“育ちの方向やペースが少し違う子”。
そのサインを丁寧に受け止めて関わることが、保育の専門性そのものです。
気になる=困る ではなく、
**「気づいたからこそ、今できることがある」**という姿勢で、子どもの育ちに寄り添っていきましょう。


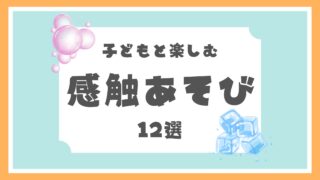
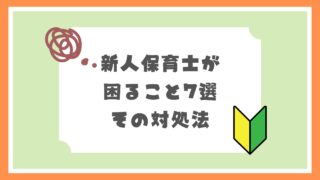
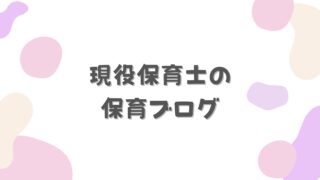
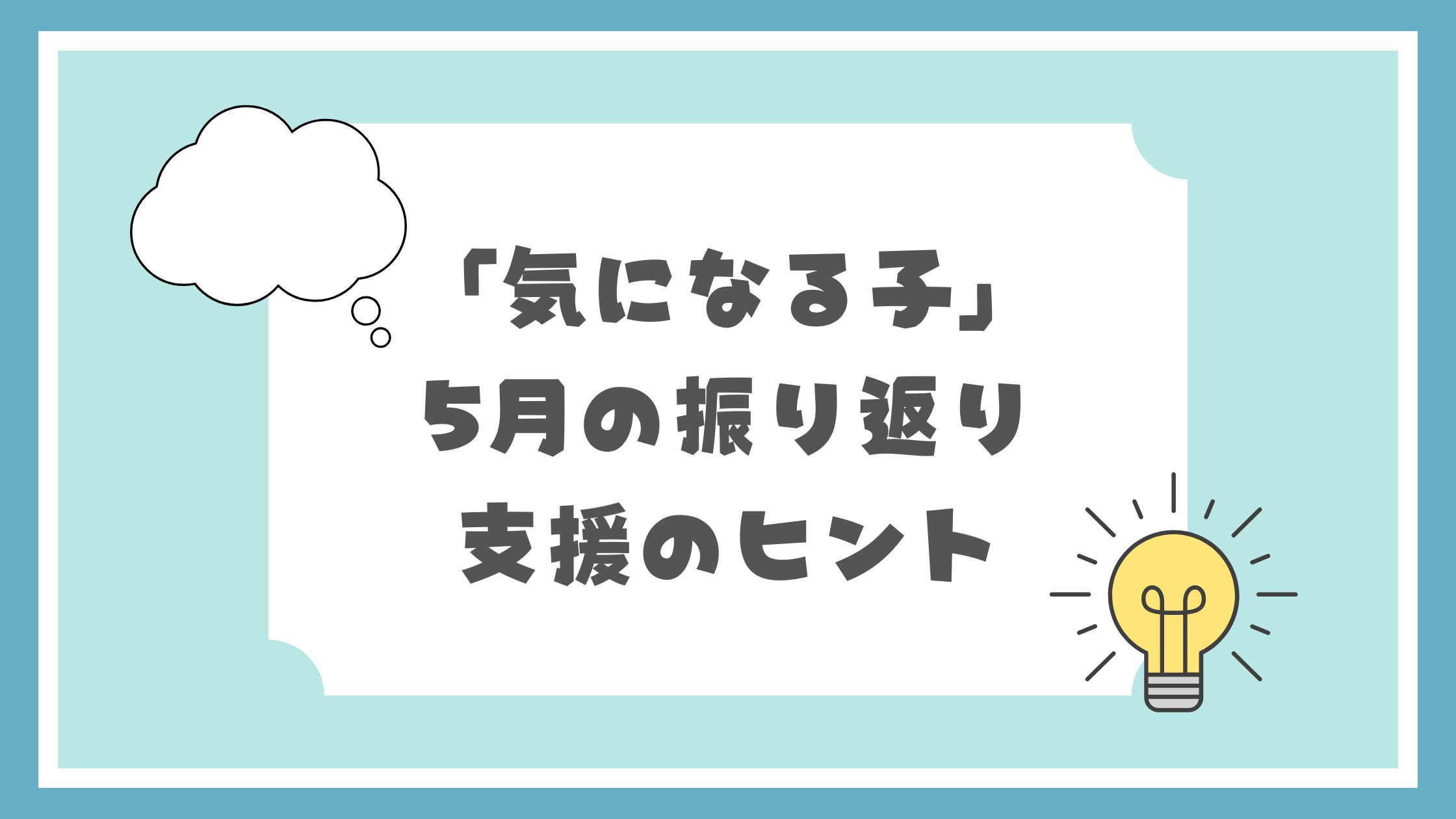
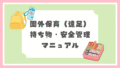

コメント