保護者対応に差が出る!連絡帳の伝え方・書き方テクニック
〜「伝わる」から「信頼される」連絡帳へ〜
保護者とのコミュニケーションの基盤ともいえる連絡帳。
園での様子を伝えるだけでなく、子どもの成長を共有し、信頼関係を築く大切なツールです。
しかし、「書く時間がない」「何を書けばいいかわからない」「伝わっていない気がする」といった声も多く聞かれます。
この記事では、伝わりやすく、信頼につながる連絡帳の書き方を、基本のポイントとテクニック別にわかりやすくご紹介します。
1. なぜ連絡帳が大事なのか?
連絡帳は、保護者が「自分の子どもがどう過ごしているか」を知る唯一の手段であることが多く、毎日読んでいる保護者も多いもの。
- 保育士と保護者が同じ方向を向くため
- 保護者の不安を軽減するため
- 小さな変化に気づき、共有するため
など、関係性を築く基礎のひとつといえます。
2. よくあるNG例と改善のヒント
| NGな例 | 改善のヒント |
|---|---|
| 今日は特に変わりありません。 | 小さなエピソードを拾い、「らしさ」を伝える。例:「おままごとでお皿を丁寧に並べていました」 |
| ○○ちゃんと仲良く遊びました。 | 遊びの内容や関わりの様子もセットで。「お店屋さんごっこでお客さん役をしていました」 |
| よく泣いていました。 | 否定的な表現は避け、背景や対応を添える。「朝は涙が出ましたが、好きなぬいぐるみを持つと落ち着きました」 |
3. 伝わる連絡帳を書く5つの基本ルール
① 「事実」+「エピソード」+「気持ち」のセットで
→ ただの出来事だけでなく、子どもの気持ちや表情も伝えると、読み手のイメージが広がります。
例:
「給食では苦手なにんじんを見て首を振っていましたが、最後に一口チャレンジして『たべた!』と誇らしげな表情でした」
② 小さな成長や“その子らしさ”に目を向ける
→ 日常の中の小さな変化こそ、保護者が知りたいポイントです。
③ ネガティブな出来事は表現を柔らかく
→ 困った行動も、成長過程の一つとして表現するのが大切。
例:
「今日は少し気持ちの切り替えに時間がかかりましたが、○○くんが声をかけてくれたことで気持ちが動きました」
④ 文章は短くてもOK。大事なのは“具体性”
→ 長文よりも、「わかりやすく、場面が浮かぶ」ことを意識しましょう。
⑤ 読み手(保護者)へのひとことを添える
→ 「○○ができてすごいですね」「ご家庭での様子もぜひ教えてください」など、一言添えるだけで印象が変わります。
4. よく使う言い回し・言い換えテクニック
| ネガティブ表現 | 言い換え例 |
|---|---|
| 泣いてばかりいた | 不安な気持ちが強く、涙が出ることもありましたが… |
| 言うことを聞かない | 自分の気持ちを強く持ち、やりたいことに集中していました |
| 集団に入れなかった | 落ち着いた場所を選び、じっくりと一人で遊んでいました |
5. 年齢別の書き方のポイント
● 0〜1歳児
- 食事・排泄・睡眠の様子が中心
- 「機嫌」「反応」「関わり」を丁寧に
- 成長段階に応じた動きや音への反応も
● 2〜3歳児
- 自我の芽生えや関わり方の変化
- 「自分でやりたい」気持ちの表現
- ごっこ遊びや模倣のエピソードなど
● 4〜5歳児
- 集団遊びや友だち関係の中でのやりとり
- 自分の気持ちを言葉にした様子
- 「できた」「がんばった」経験の共有
6. 書き手の負担を軽くする工夫
- テンプレートや定型表現を活用する
- 担当同士でネタを共有する(今日の遊びやエピソード)
- 時間を決めて書く習慣をつける(午睡中・午前のうちにメモなど)
7. まとめ|連絡帳は“子どもをつなぐ橋”
連絡帳は、子どもを通じて大人同士が信頼を育むツールです。
丁寧に言葉を重ねることで、「この先生に任せてよかった」と思ってもらえるきっかけにもなります。
伝えることに迷ったときは、「今日の○○くん・ちゃんらしい場面は?」と考えてみることが、良い文章への第一歩です。


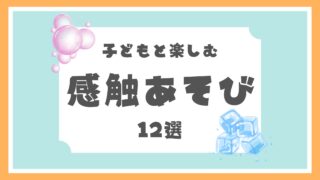
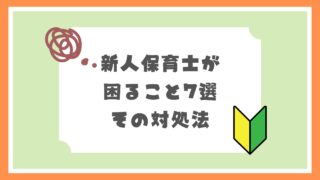
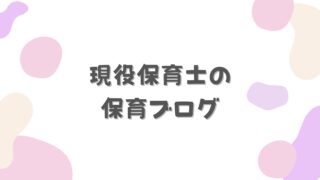
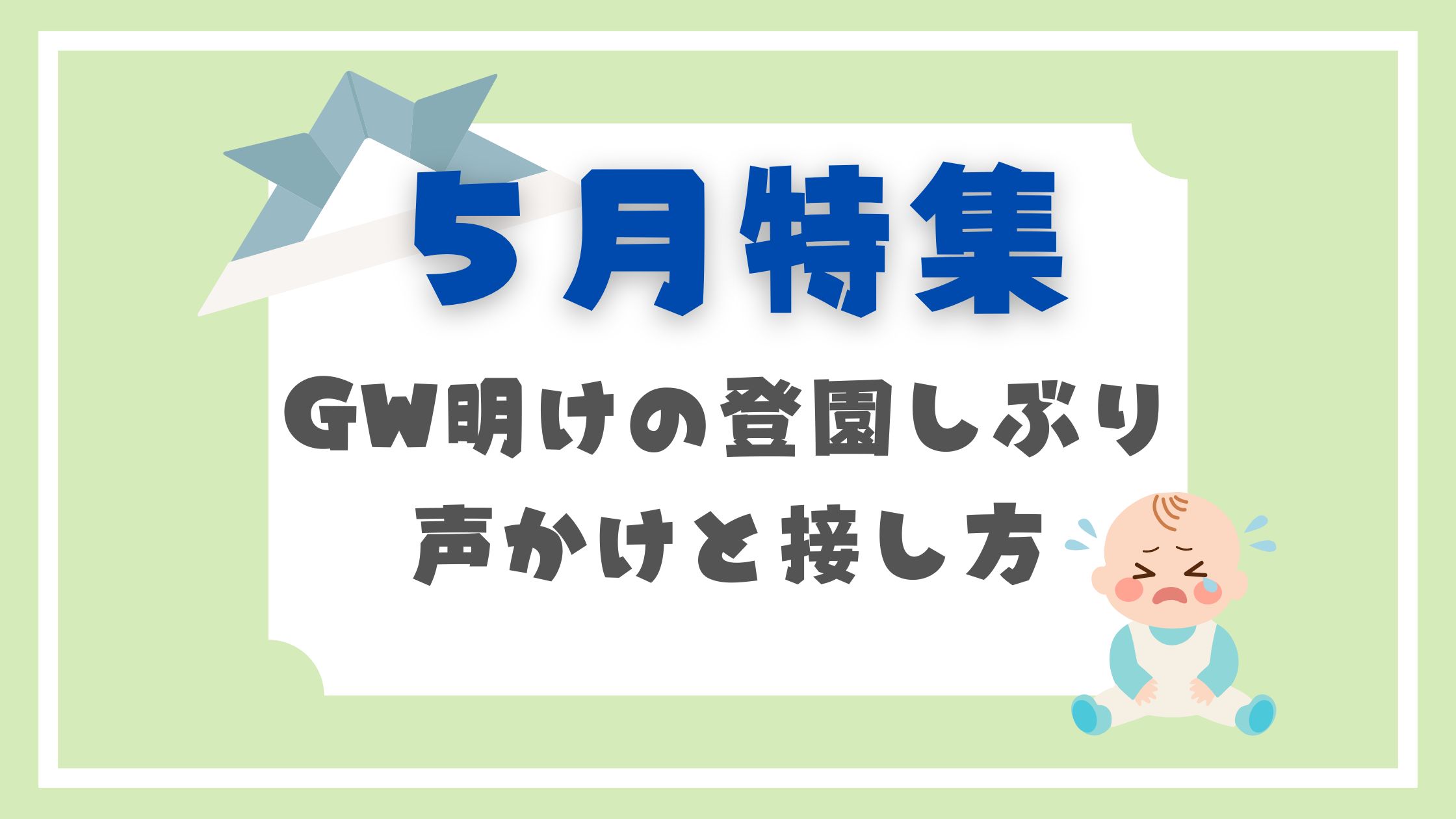
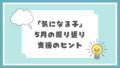
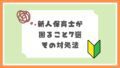
コメント