「どうしてあの子だけ寝ないんだろう…」
「寝かしつけに30分以上かかってしまう…」
そんな悩み、保育士なら一度は経験がありますよね。
今日は、私の園で実際に効果があったお昼寝テクニックを、体験談とともにご紹介します。保護者の方から聞いた“家庭での工夫”も交えているので、保護者支援にも活用できるはずです。
1. 【まずは“安心”をつくる】
■ 保育士目線
1歳児クラスの頃、なかなか寝つけなかったSくん。午睡の時間になると、毎日泣いてしまっていました。
そこで私がやったのは、「午睡前のルーティンづくり」でした。
私の園ではこうしていました:
・絵本→トイレ→水分補給→お昼寝準備(いつも同じ順番)
・その子のタオルケットの柄やぬいぐるみを“安心アイテム”に
この流れを毎日繰り返すうちに、「あ、次はねんねだね」と子ども自身が心の準備をしやすくなったようで、泣く時間がどんどん短くなりました。
■ 保護者目線
「寝かしつけが園でもおうちでも安定してきました」と、お母さんから聞いたときは本当にうれしかったです。家庭でも同じタオルや絵本を使ってくださっていたそうです。
2. 【“眠りのスイッチ”を探す】
■ 保育士目線
2歳児のMちゃんは、布団には入るもののゴロゴロ転がってなかなか寝ないタイプ。でも、“背中トントン”よりも“足首を軽くにぎる”のが心地よいとわかってから、スッと眠れるようになりました。
私の園ではこうしていました:
・「手のひらをあたためて」「足を包むようににぎる」など、子どもに合う“眠りスイッチ”を探して記録
・担任同士で共有し、だれが対応してもその子に合った関わりができるようにする
■ 保護者目線
「最近、お昼寝がスムーズなんですね」と声をかけると、「家ではなかなか寝ないんですが、園ではぐっすりで助かってます」と保護者の方も安心された様子でした。
3. 【“見守る勇気”も大切】
■ 保育士目線
入園して間もない頃、どうしてもお昼寝が苦手なYくん。私もつい、声をかけたり背中をトントンしたりしてしまっていました。
でも先輩から「まずは“見守ってみる”のも一つの手だよ」とアドバイスを受け、3日間“そばにいるだけ”を意識しました。すると、4日目にはひとりで静かに目を閉じたのです。
私の園ではこうしていました:
・泣いていなければ“あえて手を出さない”時間を作る
・「見守る姿勢」も記録に残して、成長の証として保護者に伝える
■ 保護者目線
「いつの間にか自分で寝られるようになったんですね」と成長を喜んでもらえたのが印象的でした。
4. 【“一緒に寝るふり”で安心感アップ】
■ 保育士目線
年少のKくんは、「先生が見てると寝られない…」というタイプ。でも、「せんせいもここでお昼寝するからね」と隣で“寝たふり”をすると、あっという間に夢の中へ。
私の園ではこうしていました:
・布団に一緒に入って“寝たふり”
・その子が寝ついたら、そっと離れる(タイミングが重要)
■ 保護者目線
「うちでも“ぬいぐるみを寝かせるふり”をしたら一緒に寝てくれました!」と、保護者の方もお昼寝へのハードルが下がったそうです。
5. 【“寝ない日もある”を受け止める】
■ 保育士目線
どんなに工夫しても、やっぱり寝ない日もある。3歳のTくんは、日によってテンションに波がありました。でも、その日一日どんな活動をしてきたか、体調や気分を読み取って「今日は無理に寝なくてもいいね」と声をかけると、不思議とそのあとすっと寝ることも。
私の園ではこうしていました:
・「寝ることが目的」ではなく、「体を休めること」を大切に
・無理に寝かせず、静かに過ごせる環境も準備(絵本・リラックスCDなど)
■ 保護者目線
「園で“寝なくても大丈夫な日”があると知って、家でも気持ちがラクになりました」と言っていただけたことがあります。
具体的な方法8選
1. 耳たぶをやさしく触る
▶ 指先で耳たぶをやさしくなでることで安心感が生まれ、スッと眠りに入る子が多いです。繰り返しのリズムが心地よいようです。
2. 足首を包むように軽くにぎる
▶ 不安定な子や緊張している子に効果的です。足元が温まることでリラックスし、寝つきやすくなります。
3. リラックス音楽を流す(自然音・オルゴールなど)
▶ 小さな音量で川のせせらぎやオルゴールを流すと、環境音を遮って安心できる空間になります。習慣化すると“音を聞いたら寝る”というリズムがつくれます。
4. 布団をやさしく“なでる”動作で落ち着かせる
▶ 背中やお腹ではなく、布団越しに“トントンではなく、なでる”ことで圧迫感を避けつつ心地よさを与えます。敏感な子におすすめ。
5. 一緒に布団に入り「寝たふり」をする
▶ 「見られてると眠れない」という子には、“先生も寝てる”という安心感が効果的。ほんとうに数分寝てしまう先生もいます(笑)
6. お気に入りのぬいぐるみやガーゼを持たせる
▶ 安心アイテムを持たせることで「ひとりじゃない」と感じられ、安心して寝ることができます。園と家庭で共通の物を使うとより効果的です。
7. 寝る前に必ず同じ絵本を読む(入眠儀式)
▶ 「この絵本を読んだら寝る」がルーティンになると、自然と眠気のスイッチが入るように。語りかけるように読んであげるのがコツです。
8. 頭のてっぺんをゆっくりなでる
▶ 心が落ち着き、安心感につながるスキンシップ。ゆっくりなでることで「大丈夫だよ」の気持ちが伝わります。興奮気味の子に特に有効です。
【おわりに】
お昼寝は、子どもにとって“休息”であると同時に、大人にとってもその日の保育を調整する大切な時間です。
「こうすれば絶対に寝る!」という正解はありません。でも、一人ひとりの子どもと向き合って、その子に合った“ねんねの形”を見つけていけたら、それが一番の成功なのだと思います。
保育士同士で情報を共有したり、保護者と連携したりしながら、少しずつ“ねんねの時間”が楽しみになるよう工夫していきたいですね。


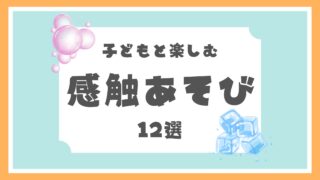
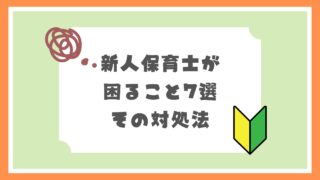
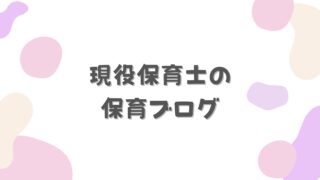
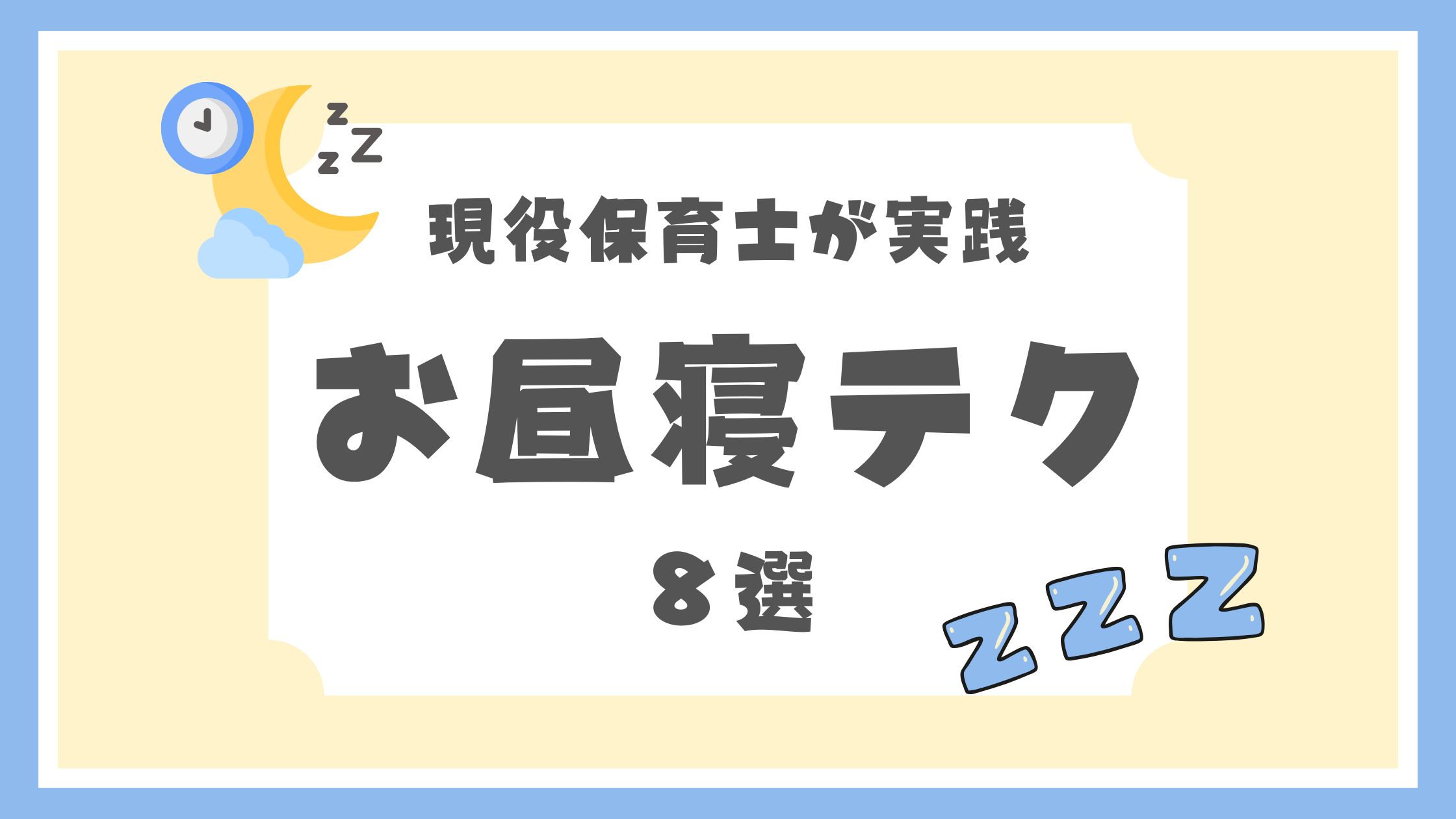
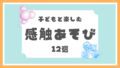
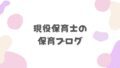
コメント