「うちの子、朝になると『行きたくない』って泣いてしまって……」
ある日、年少クラスのAくんのお母さんから相談を受けました。Aくんは朝の登園時、園の門の前で立ち止まり、お母さんの手をぎゅっと握ったまま動かなくなる子でした。
■ 保育士として見えていたAくんの姿
私の園では、朝の受け入れ時間になると、子どもたちはそれぞれ好きな遊びに向かいます。ところがAくんは、登園してもしばらくお父さんと廊下の絵本を見たり、大きな声で癇癪を起こしたり……。
お迎えに来たお母さんは「いつもすみません、家で聞かせますので、本当にすみません」とのこと。お母さんお父さんともに困り感がありました。
A君は、日中の活動中、流れが決まっていること(着替え→トイレ→ご飯→絵本→午睡)はとてもスムーズに行動できます。
私は「朝の動きをルーティン化すれば、スムーズに登園できるかもしれない。」と考えました。
■ 保護者の気持ちに寄り添いながら
Aくんのお母さんも、とても不安そうでした。「無理に行かせて大丈夫なんでしょうか?」「もしかして、合わないのかも……」という言葉も漏れていました。
私はまず、「Aくん、気持ちが切り替わった後はいつも笑顔で遊べていますよ」と伝えました。
そのうえで、「A君は、活動の流れが決まっているととてもスムーズに動けるので、朝の動きをルーティン化して見ませんか」と提案しました。
■ 小さな変化の積み重ね
その後、Aくんの保護者には、登園する→絵本を1冊読む→保育室に来るという流れを徹底してもらいました。
それからしばらくの間は、涙を流す姿がありましたが2ヶ月ほどすると、スムーズに登園できるようになりました。
また、帰りの時間に「今日は〇〇くん自分で気持ちを切り替えて遊びに入っていく事ができましたよ。」とAくんと保護者が離れた後の様子を具体的に伝えることで、保護者も少しずつ安心してくださるようになりました。
■ 笑顔の朝が来るまでに必要だったもの
Aくんが、朝自分の足で笑顔で保育室に入ることができるようになり、面談時お母さんが、少し涙ぐみながら「本当にありがとうございました」とおっしゃったのが印象に残っています。
この経験を通して私が感じたのは、保護者との連携の大切さ。
保育士と保護者が共通認識を持つことによって対応にばらつきがなく、子どもも少しずつ慣れていく事ができました。
■ 保育士として、これからも
保護者の困り感に丁寧に向き合うことで、信頼関係が育まれます。
これからも私は、子どもたちの“心の声”にはもちろん、保護者の心の声にも耳を傾け、保護者の方と共に歩んでいける保育士でいられるように「心の声」意識していきます。
※記事内のエピソードはプライバシーに配慮し、設定の一部を変更しています。


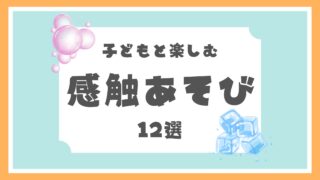
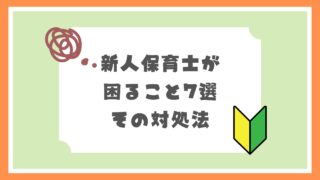
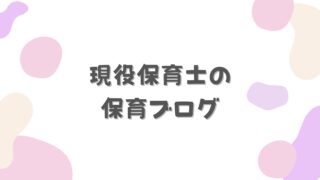
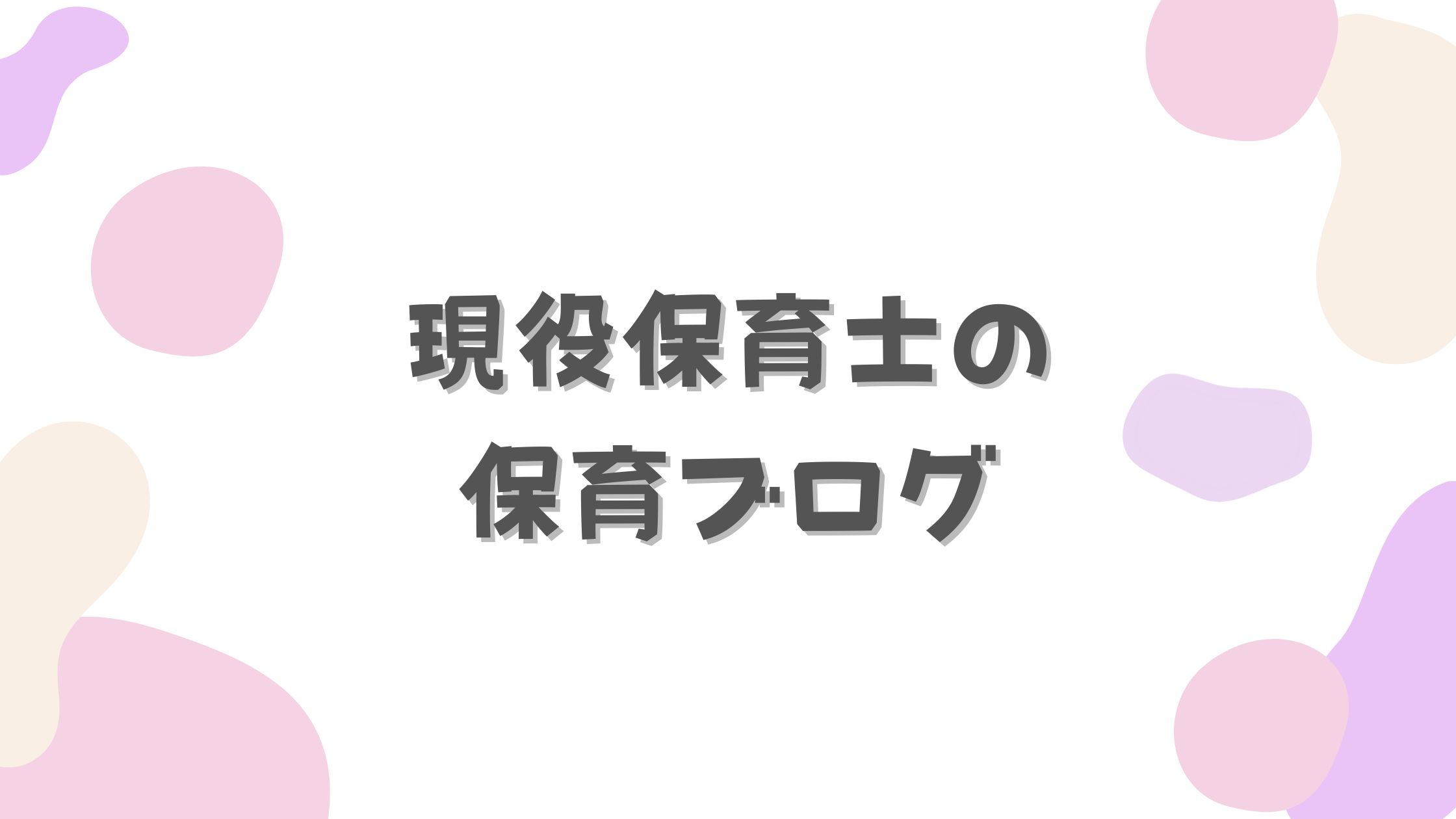
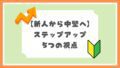
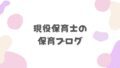
コメント