「保育って、なんだろう?」
この問いに、保育士として働いている今でも、私ははっきりとした答えを持っていません。
けれど、日々の保育の中で、「これも保育だったんだ」と感じた瞬間は、数えきれないほどあります。
今日は、私の体験を通して、“保育”とは何かをあらためて考えてみたいと思います。
失敗から始まった「関わることの意味」
新人時代、私は「子どもに何かを教えること」が保育だと思っていました。
スプーンの持ち方や、片づけの仕方、挨拶の声の出し方――どこか“正しい姿”に導こうとしていたのだと思います。
ある日、おもちゃの取り合いをしたAくんとBくんの仲裁に入った私は、「順番で使おうね」といつものセリフでその場を収めようとしました。
でもAくんは怒ったまま、私から離れていきました。
その後、ベテランの先輩がそっと声をかけてくれました。
「今、Aくんの気持ちは受け止めた? “ルール”より、“気持ち”を先に見てあげるといいよ。」
ハッとしました。私は、“こうあるべき”ばかりを伝えていて、“今その子がどう感じているか”に目を向けていなかったのです。
私の園で感じた「寄り添う保育」
私の園では、日々の出来事を“子どもの視点”でとらえることを大切にしています。
連絡帳や日誌でも、「子どもが何を感じ、どう動いたか」を中心に記録します。
ある日、年長のCちゃんが突然泣き出したことがありました。理由を尋ねると、どうやら“友だちに嫌なことを言われたけど、先生に言っていいか迷った”とのこと。
「嫌だったって思う気持ち、大事にしていいんだよ。」
そう伝えると、彼女は涙を拭いて、「明日、自分で言ってみる」と言いました。
このとき私は、「保育って、“自分の気持ちを言ってもいい”って思える場所をつくることなんだ」と感じました。
保護者と共に考える「子どもを見るまなざし」
保護者とのやり取りの中でも、「保育ってなんだろう」と考えさせられる場面は多くあります。
たとえば、Dくんのお母さんがある日、「最近、うちの子、わがままじゃないですか?」と相談に来られました。
私が思い出したのは、Dくんがブロック遊びで自分の作った作品を守ろうと必死だった姿。
「わがままというより、自分の思いを主張できるようになってきたんですよ。」とお伝えすると、
お母さんは少し驚いたように笑って、「見方を変えると、育ってるってことなんですね」と返してくれました。
保育士の役割は、保護者と一緒に“子どもの育ち”を見つめていくことでもあると、あらためて感じた瞬間でした。
保育は、教えることだけじゃない
“教えること”も大切。
でも、それだけじゃない。“気づいてもらう”“待つ”“寄り添う”といった関わりこそ、保育の根っこなのかもしれません。
子どもが泣いても、怒っても、笑っても。
その全部に価値があって、それを一緒に感じることが保育。
そんなふうに考えるようになってから、私は日々の保育にもっと“余白”を持てるようになりました。
焦らず、比べず、今その子と一緒にいる時間を大事にする。
最後に|“答えがないから、向き合い続ける”
「保育って、なんだろう?」
答えは、今も分かりません。
でも、それでいいんだと思っています。
保育には、正解がないからこそ、毎日考える価値がある。
子どもの数だけ、育ちのかたちがあって。
その一つひとつに、“今日の保育”という意味がある。
明日もまた、私は問い続けながら、保育という仕事に向き合っていこうと思います。


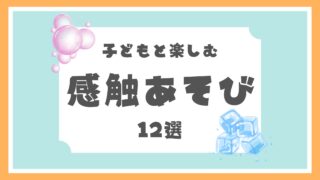
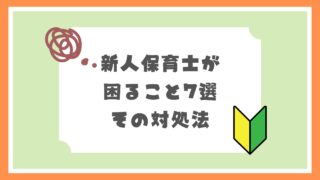
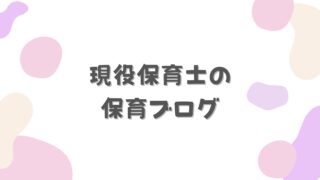
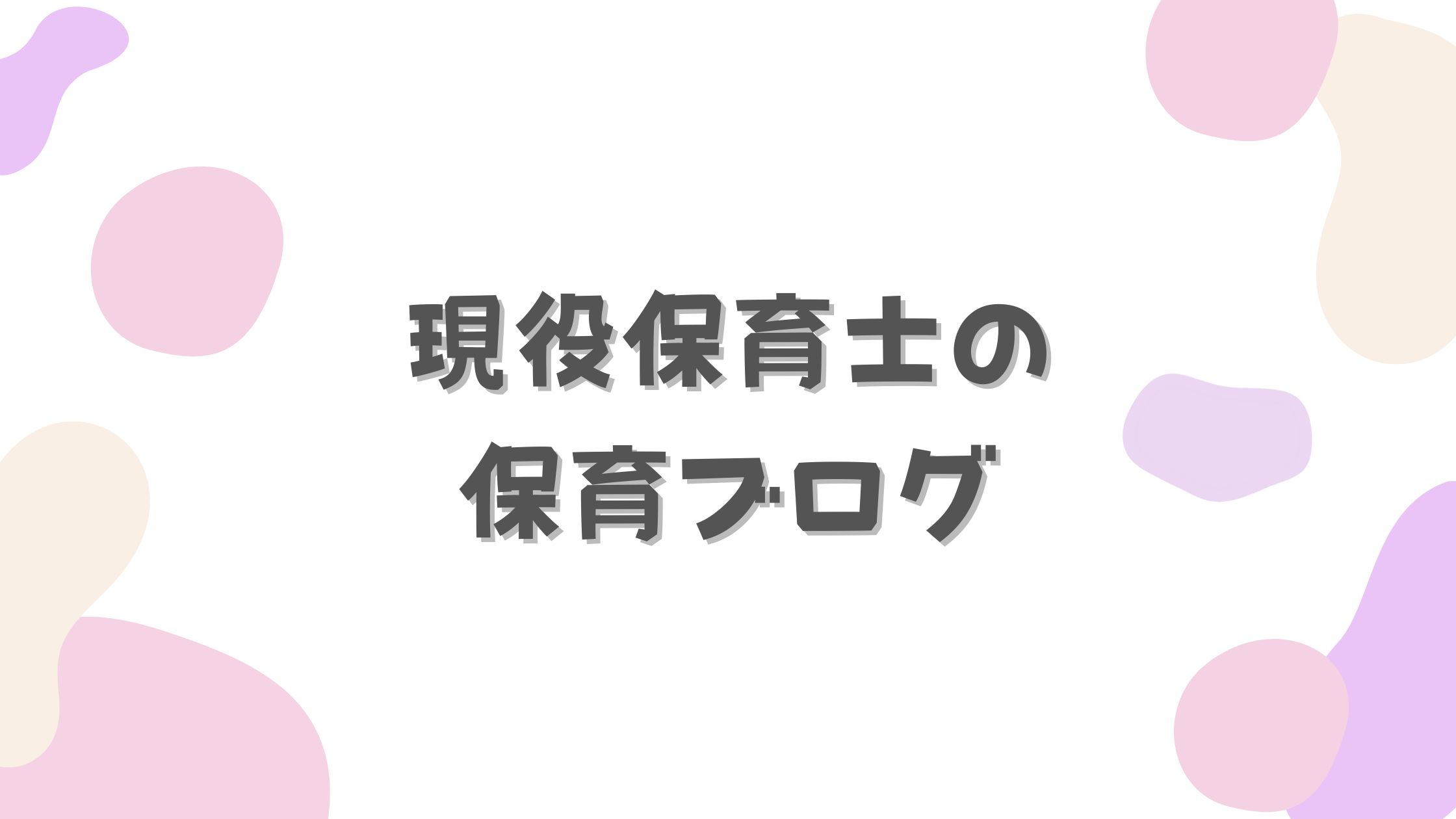


コメント