0歳児は、生まれてからの成長が著しい時期です。視覚や聴覚、触覚など五感を通して周囲の環境や人との関わりを少しずつ理解し、自分の存在を確かめながら安心感を育んでいきます。まだ言葉は出ませんが、笑顔や泣き声、手足の動きで気持ちを伝え、保育者の温かい関わりを受けることで、信頼関係が深まっていきます。
安心して過ごせる環境の中で、個々の発達段階に応じた刺激や愛情を受けながら、心と体の基礎づくりを大切にしていきます。
◎1年のねらい
保育者との安定した関係を築き、安心できる環境の中で心身の成長を促す。
一人ひとりの発達や生活リズムを大切にしながら、自分らしく生活できる力の芽生えを育む。
【第1期(4月〜6月)】
◎ねらい
新しい環境に慣れ、安心して過ごす。
保育者との信頼関係を築き、自分のペースで生活できるようになる。
◎生命
個々の生活リズムを尊重し、無理なく園生活に慣れていく。
安心できる抱っこや声かけを通して、生命への信頼感を育む。
保育者の配慮
子どもの体調や眠気、空腹など小さなサインを見逃さず、タイミングよく応じる。
生活リズムを押し付けず、家庭のリズムと連携を取りながら整えていく。
◎情緒
泣いたり笑ったりしながら、保育者に気持ちを受け止めてもらうことで安心感を得る。
自己表現の芽生えを大切にし、自信を育む。
保育者の配慮
どんな感情も受け入れ、抱っこや言葉で応えることで情緒の安定を図る。
不安なときほどゆったり寄り添い、心の安心基地になるよう努める。
◎5領域
◎健康
健康的な生活リズムを整えながら、心地よく過ごす。
体調の変化に合わせた柔軟な対応を受け、安心して生活する。
保育者の配慮
体温や皮膚の状態、表情などから体調を細かく察知し、すぐに対応する。
無理な活動をせず、休息を十分に取り入れながら一人ひとりの健康を守る。
◎人間関係
保育者との一対一の触れ合いを通して、愛着を育む。
他児への興味も芽生え始める。
保育者の配慮
スキンシップや笑顔を交えて、温かな関係づくりを意識する。
他児とのかかわりも無理なく自然な流れでつなげ、安心して過ごせるようにする。
◎環境
身の回りの環境に好奇心を持ち、自発的に関わろうとする。
安心できる場所から徐々に世界を広げる。
保育者の配慮
安全を最優先にした環境を整え、自由に探索できるようにする。
新しい環境への不安には丁寧に寄り添い、安心してチャレンジできるよう支える。
◎言葉
喃語や表情で自分を表現し、周囲から応答を受ける喜びを感じる。
保育者とのやりとりを通じて、言葉への興味を育む。
保育者の配慮
喃語や声かけに即座に反応し、言葉で丁寧に応える。
子どもの表情や声をじっくり受け止め、豊かなやりとりを重ねる。
◎表現
手足をバタバタさせたり、笑顔を見せたりしながら、自分なりの表現を楽しむ。
音やリズムなどの刺激に反応し、身体を動かすことを喜ぶ。
保育者の配慮
子どもの動きや表情に合わせ、共感したり真似したりして表現の楽しさを引き出す。
表現活動に対して制約を設けず、自由な感情の発露を大切にする。
◎食育
離乳初期の段階に応じ、食べる意欲を大切にする。
食事の時間を通して、人との関わりの温かさを感じる。
◎家庭との連携
保護者との対話を深め、子どもの生活リズムや成長を共有する。
不安や悩みに寄り添い、家庭との一体感を持った保育を心がける。
◎職員間の連携
小さな体調や感情の変化を即時に共有し、迅速に対応する。
チーム全体で情報を把握し、子どもの安心に直結する保育を行う。
◎異年齢保育
無理のない範囲で年上児の関わりを見守り、安心できる交流を支える。
異年齢児の様子を見ながら興味を引き出す機会とする。
◎長時間保育の配慮
子どもの負担を考慮し、十分な休息や安心できる空間づくりを大切にする。
長い時間園で過ごす子に、特に応答的な関わりを心がける。
【第2期(7月〜9月)】
◎ねらい
環境に慣れ、自己表現が豊かになり、他者との関わりを楽しむようになる。
情緒の安定と共に、周囲の世界に対する興味が深まる。
◎生命
生活リズムが整い、より自分でできることが増えてくる。
食事やお昼寝など、基本的な生活習慣が定着する。
保育者の配慮
子どものペースに合わせ、少しずつ自分でできることを促す。
環境の変化や新しい活動に対して不安を感じることがあれば、丁寧にサポートし安心させる。
◎情緒
保育者や友達と遊びながら、感情の表現が豊かになり、自己表現を楽しむ。
周囲の反応に興味を持ち、他者とのやりとりの中で安心感を深める。
保育者の配慮
感情に寄り添い、共感しながら安心感を与える。
新しい体験を怖がらずに楽しめるように見守りながら支える。
◎5領域
◎健康
生活習慣がさらに整い、食事やお昼寝が規則的になる。
自分で食べることに挑戦し、食事の時間が楽しみになる。
保育者の配慮
食事やお昼寝の時間に一貫性を持たせ、生活リズムを安定させる。
自分で食べることを促し、温かい言葉で見守りながらサポートする。
◎人間関係
他の子どもとの関わりが増え、お友達との遊びを楽しむようになる。
自分の気持ちを伝える力が育ち、相手の気持ちにも関心を持つ。
保育者の配慮
友達とのやりとりを見守り、トラブルがあった場合は適切に介入する。
「ありがとう」や「ごめんね」など、簡単な言葉を教えながら、他者との関係を大切にする。
◎環境
探求心が増し、身の回りのものに触れたり、遊びながら環境を楽しむ。
安全な環境の中で、自由に動き回り、物に触れて感覚を育む。
保育者の配慮
安全で興味を引く遊具や素材を用意し、自由に探索できるようにする。
新しい物に触れる時は、不安を感じないように見守り、積極的に声かけをする。
◎言葉
身近な言葉を模倣し始め、簡単な単語やフレーズを使えるようになる。
身の回りの物の名前を覚え、興味のある物に対して言葉で表現しようとする。
保育者の配慮
言葉を使ったやりとりを増やし、絵本の読み聞かせや歌を通じて言葉の世界を広げる。
子どもの言葉にすぐ反応し、正しい言葉を使えるように丁寧に教える。
◎表現
手や足を使ってリズムに合わせて体を動かしたり、楽器で音を楽しむことができるようになる。
色や形に興味を持ち、絵を描いたり、遊びを通じて自己表現を楽しむ。
保育者の配慮
音楽やリズム遊びを取り入れ、体を使った表現を楽しませる。
感覚を刺激する素材やおもちゃを使い、創造力を育てる。
◎食育
食事の時間を楽しみながら、食事の大切さや食べることへの興味を育む。
食事の習慣が身につき、子どものペースに合わせた食事環境を作る。
◎家庭との連携
家庭での生活リズムや食事習慣を理解し、園での生活と合わせていく。
保護者とのコミュニケーションを深め、育児の悩みや喜びを共有する。
◎職員間の連携
子どもの成長に合わせたサポートを職員間で共有し、情報を密に交換する。
お互いの役割を尊重しながら、チームワークで保育を進める。
◎異年齢保育
異年齢児の関わりを増やし、上のお兄さんお姉さんと触れ合う中で新しい刺激を受ける。
年上の子どものお世話を見て、学びながら自分の役割を意識する。
◎長時間保育の配慮
昼寝や休憩を十分に取り入れ、過ごしやすい環境を作る。
長時間園にいる子どもには、特に落ち着いた環境とサポートを提供する。
【第3期(10月〜12月)】
◎ねらい
言葉や感情をより豊かに表現できるようになり、他者との関わりがさらに楽しくなる。
自分の気持ちを伝えたり、相手を思いやることができるようになる。
◎生命
自分でできることが増え、基本的な生活習慣がしっかり定着する。
食事やお昼寝のリズムが安定し、健康的な生活が送れるようになる。
保育者の配慮
子どもが自分でできることを見守り、必要に応じてサポートする。
生活の中で、自分でできたことに対して褒めて自信を育む。
◎情緒
感情の表現が豊かになり、喜怒哀楽をしっかりと感じることができる。
周囲の人々と共感し合い、情緒的な安定感を深める。
保育者の配慮
子どもの気持ちを大切にし、感情を表現できるように励ます。
情緒が不安定な時には、温かい言葉と共に寄り添い、安心感を与える。
◎5領域
◎健康
動きが活発になり、運動能力が向上する。
食事も自分でできることが増え、積極的に食べる意欲が高まる。
保育者の配慮
食事の時間に自分で食べる楽しさを感じられるようサポートする。
運動や遊びの時間をしっかり取ることで、心身の健康を育む。
◎人間関係
他の子どもとのやり取りが増え、友達と一緒に遊ぶことが楽しくなる。
自分の気持ちを伝え、他者の気持ちを考えることができるようになる。
保育者の配慮
友達と遊ぶ中で、感情や気持ちを大切にしながら仲間意識を育む。
困った時には適切にサポートし、自己主張や他者との関わり方を学ぶ。
◎環境
周囲の環境に興味を持ち、探索することがさらに活発になる。
自然との触れ合いや、日常生活の中で新しい発見を楽しむ。
保育者の配慮
周囲の環境に積極的に触れ合い、自然や日常の物に興味を持たせる。
安全に配慮しながら自由に探索できるよう、環境を整える。
◎言葉
言葉で自分の気持ちや考えを表現できるようになる。
周囲の人々の言葉を模倣し、会話の中で学びながら言語の発達を促す。
保育者の配慮
子どもが言葉を使う場面を増やし、会話のキャッチボールを楽しむ。
新しい言葉を覚える過程を応援し、語彙力を広げる手助けをする。
◎表現
絵や音楽、身体を使って表現することが楽しくなる。
自分の気持ちを言葉や動き、音で表現しようとする。
保育者の配慮
自由な表現活動を提供し、子どもの思いを引き出す。
音楽や絵の具などを使って、創造力を豊かに伸ばす。
◎食育
食事の時間が楽しく、食べることが心身の成長を支えることを学ぶ。
食事を自分で選び、食べることの大切さを実感する。
◎家庭との連携
家庭の食事習慣や日常生活を理解し、園での生活との一貫性を持たせる。
保護者と一緒に子どもの成長を確認し、共に育て合う。
◎職員間の連携
情報をこまめに共有し、子ども一人ひとりに適した保育を行う。
お互いの経験や意見を大切にし、より良い保育環境を作る。
◎異年齢保育
異年齢児の関わりを深め、年上児との交流を通じて社会性を育む。
年上児と一緒に遊ぶことで、模倣や学びが得られる。
◎長時間保育の配慮
子どものペースを守り、長時間保育でもストレスを感じないよう配慮する。
必要に応じて、リラックスできる時間や空間を提供する。
【第4期(1月〜3月)】
◎ねらい
冬の寒さにも負けず、体力がつき、他者との関わりがさらに深まる。
自分の感情や思いを伝える力が育ち、より豊かな表現を楽しむ。
◎生命
自分でできることが増え、日常生活において一人でできることがさらに多くなる。
身体を動かすことを楽しみ、外遊びや室内遊びで体力が養われる。
保育者の配慮
子どもが自分でできることを褒めて、自信を持たせる。
寒い季節でも十分に体を動かせるよう、室内外での遊びをバランスよく提供する。
◎情緒
感情表現がさらに豊かになり、喜びや悲しみなど、さまざまな感情をしっかりと表現できる。
保育者との信頼関係を深め、心の安定を保ちながら新しい経験に挑戦する。
保育者の配慮
感情が高ぶった時には、その気持ちを受け止めて安心させる。
楽しい時や悲しい時、どんな時でも寄り添いながら対応し、情緒的な支えとなる。
◎5領域
◎健康
体力がつき、寒さに対する耐性が強くなっていく。
外遊びや体を使う遊びを通して、心身共に健やかな成長を促す。
保育者の配慮
寒い季節でも活発に体を動かせるよう、暖かい服装や準備を整える。
外遊びや室内遊びで、身体を自由に動かしながら体力を養う。
◎人間関係
友達との関わりが増え、互いに気持ちを共有する楽しさを感じる。
他者の感情や意思を理解し、協力することができるようになる。
保育者の配慮
友達との関わりを見守り、積極的に声をかけながら社会的なやりとりを促す。
ケンカやトラブルがあった時には、冷静に介入し、子どもたちに解決の方法を示す。
◎環境
自然や物に対する興味が深まり、身の回りの環境を探求する力が育つ。
周囲の環境に対する理解が進み、物の名前や使い方に対する認識が広がる。
保育者の配慮
子どもが自分で環境を探索できるよう、安全で興味を引く遊具や道具を準備する。
環境に対する好奇心を育てるため、様々な物に触れさせる。
◎言葉
自分の気持ちを言葉で表現できるようになり、周囲との会話が豊かになる。
新しい言葉を覚えて使うことが楽しくなり、言葉のやり取りが積極的になる。
保育者の配慮
言葉を使う場面を増やし、会話を楽しむことができるようにサポートする。
絵本の読み聞かせや歌を通して、言葉への興味を育てる。
◎表現
自分の思いや感情を、体や声、絵を通じて表現できるようになる。
感情を豊かに表現することが楽しくなり、遊びの中で創造力を発揮する。
保育者の配慮
体を使った表現遊びを通じて、身体の動かし方やリズム感を育てる。
絵の具やクレヨンを使って自由に表現できるよう、環境を整える。
◎食育
食事の時間を楽しみながら、食べることの大切さを実感する。
自分で食べることが楽しくなり、食べ物に対する興味を深める。
◎家庭との連携
家庭での食習慣や生活リズムを確認し、園での生活に反映させる。
子どもの成長を家庭と共有し、保護者と連携して支援を行う。
◎職員間の連携
職員間で子どもの成長に関する情報を共有し、個々の発達を見守る。
連携を深めることで、より一貫した保育を提供する。
◎異年齢保育
異年齢の子どもとの交流を通して、年上の子どもから学び、年下の子どもをサポートする。
異年齢児との関わりが、社会性を育み、他者への思いやりを深める。
◎長時間保育の配慮
長時間保育を受ける子どもに対して、リラックスできる環境と時間を提供する。
生活リズムを崩さないよう、ゆっくりとした時間の使い方を心がける。
まとめ
この一年間で、子どもたちは身体の発達と共に感覚や情緒も豊かに育まれていきます。保育者のやさしい声かけや抱っこ、スキンシップを通じて安心感を得ることで、心の安定と発達の基盤が築かれていきます。
個々のペースを尊重しながら、五感を刺激する遊びや生活の中でのふれあいを大切にし、一人ひとりの健やかな成長を丁寧に支えていきます。


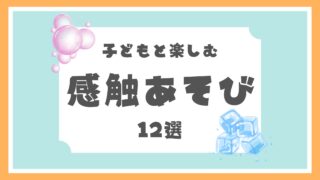
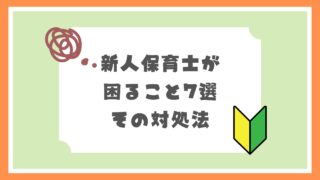
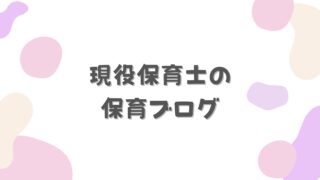



コメント