1歳児は、歩き始めや言葉の芽生えが進む時期で、自分で動きたい、知りたいという好奇心が強くなります。周りの大人や友だちの様子をよく観察し、まねをすることで少しずつ新しい動きや言葉を身につけていきます。まだまだ自分の気持ちをうまく伝えられず、泣いたり怒ったりすることも多いですが、保育者がそっと寄り添いながら気持ちを受け止めることで安心感を深めていきます。
安心できる環境の中で、自分のペースでいろいろなことに挑戦し、豊かな感性や基本的な生活習慣の基礎を育むことを大切にしていきます。
◎1年のねらい
1歳児の一年を通じて、言葉や感情の表現が豊かになり、自己表現や他者との関わりが広がる。
体力がつき、基本的な生活習慣が整い、周囲とのコミュニケーションが楽しめるようになる。
遊びや活動を通して、成長と発達を支援し、心身ともに安定した環境で育つことを目指す。
【第1期(4月〜6月)】
◎ねらい
自己表現の幅が広がり、周囲との関わりが増える。
自分の気持ちを言葉や表情で表現し、周りの人とのコミュニケーションが楽しめるようになる。
生活習慣が安定し、日常の中でできることが増える。
◎生命
体力がつき、歩くことや走ることが楽しくなる。
食事や排泄など、基本的な生活習慣への意欲が見られるようになる。
保育者の配慮
子どもが自分でできた経験を喜び合い、自信へとつなげる。
生活リズムを整え、無理なく習慣づけられるよう支援する。
◎情緒
自分の気持ちを言葉や表情で伝えようとする姿が見られるようになる。
泣いたり笑ったりしながら、保育者に気持ちを受け止めてもらうことで安心感を得る。
保育者の配慮
どんな感情も受け入れ、抱っこや言葉で応えることで情緒の安定を図る。
不安なときほどゆったり寄り添い、心の安心基地になるよう努める。
◎5領域
◎健康
歩行や走ること、登ることに意欲的になる。
外遊びを通して全身を使った運動が楽しくなる。
保育者の配慮
安全な環境を整え、自由に体を動かす機会を大切にする。
疲れた様子にも気を配り、適切な休息をとれるようにする。
◎人間関係
保育者や友達とのやりとりに喜びを感じるようになる。
簡単なやりとりや模倣を通して、他者への関心が深まる。
保育者の配慮
子どもの気持ちに応え、相手との関わりを促すようにする。
トラブルが起きたときには仲立ちし、思いを言葉にする手助けをする。
◎環境
身近な自然物や玩具への興味が高まる。
見たり触れたりしながら探索することに夢中になる。
保育者の配慮
安全で自由に探索できる環境を整える。
興味に応じた遊びや体験を一緒に楽しむ姿勢を持つ。
◎言葉
簡単な単語を使って自分の思いを表現しようとする。
身近な人の話しかけに喜んで応じるようになる。
保育者の配慮
たくさん語りかけ、子どもの発語を引き出す。
言葉のやりとりが楽しいと感じられるような関わりを心がける。
◎表現
音やリズムに合わせて体を動かすことを楽しむ。
クレヨンや粘土などを使って自由な表現を楽しむ。
保育者の配慮
表現する喜びを受け止め、過程を大切にする。
描いたり作ったりした作品に共感して声をかける。
◎食育
自分で食べたい気持ちが育ち、手づかみやスプーンを使おうとする。
食べ物の好き嫌いが出始めるが、興味を持って食事を楽しもうとする。
保育者の配慮
食べる楽しさを共有し、無理に食べさせず興味を広げる関わりをする。
一人ひとりのペースを尊重して、できたことを認める。
◎家庭との連携
生活リズムや食事の状況を家庭と共有し、一貫した支援を行う。
子どもの成長や発達に応じた対応を家庭と連携して進める。
◎職員間の連携
子ども一人ひとりの成長過程を共有し、保育の方針を統一する。
日々の気づきを報告し合い、柔軟に保育を進める。
◎異年齢保育
年上の子どもに憧れ、真似をすることで新しい行動を学ぶ。
年下の子どもに優しく接する機会を持ち、思いやりの心が育つ。
保育者の配慮
異年齢での関わりを温かく見守り、サポートする場面を適切に提供する。
◎長時間保育の配慮
安心して長い時間を過ごせるよう、個々のペースに合わせて休息や活動のリズムを整える。
特に夕方以降は、落ち着いた雰囲気づくりを心がける。
【第2期(7月〜9月)】
◎ねらい
身近な人との関わりを深めながら、自己主張が活発になる。
自分でやりたいという意欲が強くなり、様々な活動に挑戦しようとする。
暑さに負けず、夏ならではの遊びや体験を楽しむ。
◎生命
水遊びや戸外活動を通じて、体を動かす楽しさを味わう。
体調の変化に気づき、自分の不快感を伝えられるようになる。
保育者の配慮
熱中症や感染症予防に配慮し、健康観察を丁寧に行う。
「暑いね」「気持ちいいね」など子どもの感じたことに共感して言葉を添える。
◎情緒
自分の気持ちを強く表現し、受け止めてもらうことで安心感を深める。
失敗しても再挑戦する姿が見られるようになる。
保育者の配慮
感情の起伏を否定せず、気持ちを言葉にして受け止める。
「やってみよう」「大丈夫だよ」と挑戦する気持ちを励ます。
◎5領域
◎健康
暑さに負けず、戸外活動や水遊びを楽しむ。
汗をかいた後の着替えや水分補給に自ら取り組もうとする。
保育者の配慮
適切な水分補給・休息を促しながら、安全に活動できるようにする。
衣服の着脱も手伝いながら、自立心を育む。
◎人間関係
友達とのやりとりが増え、簡単な貸し借りやまねっこ遊びを楽しむ。
友達との衝突も経験しながら、関わり方を学んでいく。
保育者の配慮
トラブル時は一方的に叱るのではなく、気持ちの代弁を心がける。
友達との楽しい関わりをたくさん経験できるよう援助する。
◎環境
水や砂、自然物に触れて、感触や音を楽しむ。
夏ならではの自然現象(セミの声、夕立など)に興味を持つ。
保育者の配慮
発見や感動を一緒に共有し、子どもの「なぜ?」「おもしろい!」を大切にする。
活動場所の安全確認を徹底し、自由に探索できる環境を整える。
◎言葉
「いや」「やる」など、自己主張の言葉が増える。
友達や大人とのやりとりの中で、簡単な会話を楽しむ。
保育者の配慮
子どもの言葉を繰り返したり広げたりして、やりとりを豊かにする。
否定語も受け止め、「自分で伝えられたね」と肯定的に関わる。
◎表現
水や砂、絵の具などを使ったダイナミックな表現活動を楽しむ。
音楽やリズムに合わせて体を動かす表現が活発になる。
保育者の配慮
活動の過程そのものを楽しめるようにし、結果を求めすぎない。
思いきり表現できるように、十分な素材や広い空間を用意する。
◎食育
夏野菜や季節の食べ物に興味を持ち、食べることを楽しむ。
食事の場面で「自分で食べたい」という気持ちがより強くなる。
保育者の配慮
旬の食材を使った食育活動を取り入れ、五感を使った体験を大切にする。
自分で食べられることを喜び、自立を促す関わりを心がける。
◎家庭との連携
夏の体調管理(汗、食欲不振など)について情報共有を密に行う。
家庭での生活リズムや遊びについても相談しながら一緒に支える。
◎職員間の連携
水遊びや戸外活動時の安全管理を徹底するため、情報共有を密にする。
子どもの小さな変化にも気づき、チームで柔軟に対応する。
◎異年齢保育
年上の子どもの遊びに刺激を受け、やってみようとする意欲が育つ。
年下の子どもに対して、自然と優しい行動を見せる場面が見られる。
保育者の配慮
異年齢での遊びの中で無理をさせず、それぞれの良さを認め合う関わりをする。
◎長時間保育の配慮
活動後はしっかり休息を取り、体力を回復できるようにする。
夕方以降は静かな遊びを取り入れ、心身をリラックスさせる。
【第3期(10月〜12月)】
◎ねらい
身近な環境や人との関わりを深めながら、好奇心を広げていく。
自分でできることが増え、達成感を味わう経験を重ねる。
季節の変化に気づき、自然との触れ合いを楽しむ。
◎生命
体をたくさん動かし、丈夫な体づくりを楽しむ。
寒暖差にも対応し、自分の体調変化に気づこうとする。
保育者の配慮
寒さや気温差に配慮し、衣服調節をこまめに行う。
「寒いね」「手が冷たいね」など、子どもの感じたことを言葉にして共感する。
◎情緒
身近な人との信頼関係がより深まり、甘えたり自立したりを行き来する。
うまくいかない気持ちも表現しながら、自分なりに整理できるようになる。
保育者の配慮
甘えたい気持ちにはしっかり応え、自立心を見守りながら支える。
感情の波を受け止めつつ、安心して挑戦できるよう励ます。
◎5領域
◎健康
戸外でのびのびと体を動かし、持久力やバランス感覚を育む。
手洗いやうがいを生活習慣として身につけようとする。
保育者の配慮
寒い時期でも体を動かす機会を確保し、健康への意識を育む。
手洗いやうがいを一緒に楽しく行い、習慣化をサポートする。
◎人間関係
友達とのやりとりが深まり、簡単なやりとりややさしさの芽生えが見られる。
友達との関わりの中でルールや順番を意識し始める。
保育者の配慮
関わりの中で生じる喜びやトラブルを丁寧に受け止め、仲立ちをする。
友達の存在を大切に思う気持ちを育む援助をする。
◎環境
落ち葉やどんぐりなど、秋の自然物に触れて遊びを広げる。
季節の行事(運動会、ハロウィンなど)を経験し、社会との関わりに興味を持つ。
保育者の配慮
自然物を使った遊びや制作活動を取り入れ、豊かな感性を育む。
季節の行事を無理なく楽しめるよう、子どもに合った内容にする。
◎言葉
自分の気持ちや要求を言葉で伝えようとする場面が増える。
保育者や友達の言葉に興味を持ち、まねて使おうとする。
保育者の配慮
子どもの言葉をよく聞き、適切な言葉のモデルを示しながら応答する。
子どもが話そうとする意欲を大切にし、温かく見守る。
◎表現
秋の自然や行事をテーマにした制作や表現遊びを楽しむ。
イメージを広げながら、自由な発想で表現する喜びを味わう。
保育者の配慮
「こうしなさい」と型にはめず、自由な表現を尊重する。
子ども一人ひとりの表現を受け入れ、肯定的な言葉をかける。
◎食育
秋の味覚(栗、さつまいも、きのこなど)に触れ、食べることを楽しむ。
食べ物の香りや手触りを感じながら、食への興味を広げる。
保育者の配慮
旬の食材を使ったクッキング保育や試食体験を取り入れる。
食への関心や感謝の気持ちが自然に育つよう、丁寧に関わる。
◎家庭との連携
寒くなる時期の体調管理について、家庭と連携して見守る。
食事・睡眠・排泄など、家庭での様子も共有しながら子どもの成長を支える。
◎職員間の連携
行事や日々の活動の中で、子ども一人ひとりの様子をこまめに伝え合う。
小さな変化を見逃さず、チームで柔軟に対応する。
◎異年齢保育
年上の子どもに憧れ、まねっこする中で新たな遊びに挑戦する。
年下の子に対して自然と優しく関わろうとする姿が見られる。
保育者の配慮
年齢や発達に応じた役割を持たせ、自信や達成感を育む。
◎長時間保育の配慮
季節の変わり目に合わせた体調管理を徹底する。
夕方以降は、落ち着いた遊びや絵本の読み聞かせを取り入れて心を休める。
【第4期(1月〜3月)】
◎ねらい
自分の思いを表現しながら、身近な人との信頼関係をより深める。
簡単な生活習慣が身につき、自信をもって取り組もうとする。
1年の成長を感じながら、新しい環境への期待を育む。
◎生命
寒さに負けず、体を動かす心地よさを味わう。
体調の変化に気づき、簡単な自己管理ができるようになっていく。
保育者の配慮
寒さ対策をしながらも戸外活動を取り入れ、健康な体づくりを支える。
子どもの体調変化に敏感になり、早めに対応できるよう心がける。
◎情緒
進級への期待や不安を受け止めながら、安心して過ごす。
失敗や葛藤も受け止め、自己肯定感を高める。
保育者の配慮
子ども一人ひとりのペースを尊重し、安心できる言葉かけや態度で寄り添う。
気持ちを表現できたときは十分に認め、自信へとつなげる。
◎5領域
◎健康
戸外遊びや運動遊びで体力を養い、寒さに負けない体づくりをする。
着脱や排泄など、生活習慣の自立に向かって取り組む。
保育者の配慮
着脱やトイレの成功体験を丁寧に支え、自立心を育てる。
できた喜びを共有し、達成感を味わえるようにする。
◎人間関係
友達とのかかわりを楽しみながら、ルールや順番を意識し始める。
トラブルを経験しながらも、仲直りのきっかけをつかもうとする。
保育者の配慮
友達との関係の中で生まれる喜びや葛藤を丁寧に受け止める。
仲直りのプロセスを支援し、相手の気持ちを考える力を育む。
◎環境
冬ならではの自然(霜柱、雪など)に興味を持ち、触れて遊ぶ。
身近な環境に対する好奇心を広げ、発見を楽しむ。
保育者の配慮
自然現象を一緒に楽しみながら、発見や驚きを言葉にして共有する。
興味を持ったものを深められるような活動や環境を用意する。
◎言葉
「○○したい」「○○いや」など、自分の気持ちを言葉で表現しようとする。
簡単な会話のキャッチボールを楽しむ。
保育者の配慮
子どもの発する言葉をじっくり聞き、共感しながら返す。
子どもの伝えたい気持ちをくみ取り、言葉のやりとりを広げる。
◎表現
絵や制作活動を通して、自分なりの表現を楽しむ。
音楽やリズムに合わせて体を動かす喜びを味わう。
保育者の配慮
子ども一人ひとりの表現を認め、自由な発想を大切にする。
リズム遊びや表現活動を無理なく楽しめるよう、環境を整える。
◎食育
冬の食材(大根、白菜、みかんなど)に触れ、旬を感じる。
あたたかい食事の心地よさを味わいながら、食べる喜びを深める。
保育者の配慮
食材の由来や旬を伝えながら、食事への興味を広げる。
食事の場面で「おいしいね」と共感し、楽しい雰囲気を作る。
◎家庭との連携
進級に向けた準備(生活リズムの見直し、身の回りのことの練習など)について連携する。
家庭と園で子どもの成長を喜び合い、不安な気持ちも共有して支える。
◎職員間の連携
子ども一人ひとりの成長や気持ちを丁寧に共有する。
進級に向けて無理なくステップアップできるよう、チームで支援する。
◎異年齢保育
年上の子どもに刺激を受けながら、あこがれの気持ちを持つ。
年下の子にやさしく関わろうとする姿を受け止める。
保育者の配慮
年上児の姿を見て、自然な形で「やってみたい」気持ちが育つよう支援する。
◎長時間保育の配慮
年度末に向けた変化に配慮しながら、ゆったりと安心して過ごせる環境を整える。
夕方以降は、心が落ち着く活動(絵本、手遊びなど)を中心に行う。
まとめ
この一年間で、子どもたちは自分で歩く、話すといった身体的・言語的な成長だけでなく、保育者や友だちとのやりとりを通じて心の成長も促されます。泣いたり笑ったりしながら自分の気持ちを少しずつ表現し、他者との関わりの楽しさや安心感を味わうことで、基本的な信頼感が築かれていきます。
保育者は子どもたちの小さな変化や成長を見逃さず、丁寧に受け止め、生活や遊びを通して自分でやってみたい気持ちを支えながら、心身ともに健やかな成長を促していきます。


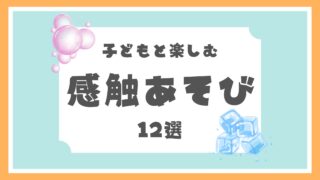
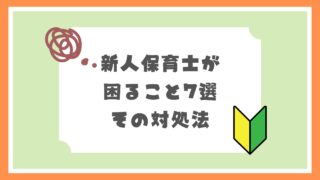
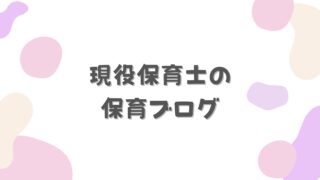



コメント