2歳児は、「自分でやりたい」「見て、聞いて、試してみたい」という気持ちが育ち、さまざまなことに挑戦し始める時期です。身の回りのことへの関心が広がり、言葉の獲得や運動機能の発達も著しく見られます。同時に、自己主張が強くなり、思いがぶつかって友達とのトラブルが起きることもありますが、こうした経験を通して他者とのかかわり方を学んでいきます。
まだ気持ちをうまく言葉で伝えることが難しい時期だからこそ、保育者が一人ひとりの思いや表現に丁寧に寄り添い、安心して自分を出せる環境を整えていくことが大切です。
◎1年のねらい
自分でできることを喜び、生活習慣の自立に向かって意欲的に取り組む。
身近な大人や友達との関わりの中で、自己表現や協調性を育む。
【第1期(4月〜6月)】
◎ねらい
新しい環境に慣れ、安心して過ごす。
保育者や友達と関わりながら、自分の気持ちを表現する喜びを味わう。
◎生命
身の回りのことに興味を持ち、できることを少しずつ自分でやろうとする。
健康な生活リズムを整え、体調の変化に気づく力を育てる。
保育者の配慮
できることを焦らず見守り、「やってみたい」気持ちを大切にする。
生活リズムが安定するよう、無理のないスケジュールで過ごす。
◎情緒
保育者に受け止められることで、安心感を持って自己を表現する。
自分の気持ちを言葉や行動で伝える経験を重ねる。
保育者の配慮
不安な気持ちを受け止め、抱っこや言葉で安心感を与える。
言葉にならない気持ちもくみ取り、温かく応答する。
◎5領域
◎健康
外遊びや運動を通して、体を動かす楽しさを味わう。
手洗い・うがい・排泄などの生活習慣に取り組み、自立に向かう。
保育者の配慮
体をたくさん動かせる環境を整え、安全に配慮しながら活動を促す。
生活習慣は手助けしながら少しずつ自立に導く。
◎人間関係
保育者との愛着関係を深め、安心して友達とのかかわりを広げる。
友達とのやりとりを通して、喜びや葛藤を経験する。
保育者の配慮
子ども同士のやりとりを温かく見守り、必要に応じて仲立ちする。
友達との関わりが楽しいと感じられるよう、共感を大切にする。
◎環境
身の回りの自然や遊具に興味を持ち、触れて遊ぶ。
季節の変化や身近な出来事に関心を広げる。
保育者の配慮
自然や環境の変化に気づけるよう、一緒に発見し喜ぶ。
興味を持ったものを深められるような体験や活動を取り入れる。
◎言葉
自分の気持ちや要求を、言葉で伝えようとする。
簡単な会話のキャッチボールを楽しむ。
保育者の配慮
子どもの言葉をしっかり受け止め、丁寧に応答する。
子ども同士の会話にも耳を傾け、気持ちのやりとりを支援する。
◎表現
音楽やリズムに合わせて自由に体を動かす楽しさを味わう。
絵や制作活動に親しみ、自分なりの表現を楽しむ。
保育者の配慮
表現の意欲を大切にし、自由に表現できるよう見守る。
完成度にこだわらず、過程を認めて喜びを共有する。
◎食育
春の食材(たけのこ、いちごなど)に興味を持ち、食への関心を深める。
食事の場面を楽しく過ごし、食べる意欲を育む。
保育者の配慮
旬の食材や食事の楽しさを伝えながら、意欲的に食べられるよう支える。
「食べるって楽しいね」と共感しながら食事の時間を大切にする。
◎家庭との連携
新しい生活リズムや園での様子について情報を共有し、安心して過ごせるようにする。
子どもの不安や戸惑いを一緒に受け止め、支え合う。
◎職員間の連携
新しい環境に慣れる過程を丁寧に見守り、職員間で子どもの様子をこまめに共有する。
個々の子どもに合わせた援助をチームで工夫していく。
◎異年齢保育
年上の子どもの姿にあこがれを持ち、自分もやってみようとする。
年下の子どもにやさしく接しようとする気持ちが芽生える。
保育者の配慮
年上児と関わる機会を大切にし、自然なかかわりが広がるよう支援する。
◎長時間保育の配慮
新しい生活に慣れるまでは、ゆったりとした時間を多く設ける。
夕方は落ち着いて過ごせるよう、絵本や静かな遊びを取り入れる。
【第2期(7月〜9月)】
◎ねらい
夏の自然や行事に親しみ、のびのびと体を動かして遊ぶ。
自分の思いを言葉や態度で表現しながら、友達との関わりを楽しむ。
◎生命
暑さに負けず、健康に過ごすための生活リズムを身につける。
自分の体の変化や疲れに気づき、休息や水分補給の必要性を理解する。
保育者の配慮
体調や汗の状態に気を配り、こまめに休息や水分補給を促す。
無理をせず、その子に合ったペースで活動できるようにする。
◎情緒
夏ならではの活動や経験を通して、喜びや驚きを感じる。
友達とのやりとりの中で、自分の思いを伝えたり、相手に配慮したりする姿を育む。
保育者の配慮
子どもの小さな発見や感情の動きを受け止め、共感をたくさん返す。
トラブルの場面でも子どもの思いを尊重し、安心できる関係づくりを大切にする。
◎5領域
◎健康
夏ならではの遊び(水遊び、プール遊び)を安全に楽しむ。
汗をかいたら着替える、帽子をかぶるなど、健康への意識を育む。
保育者の配慮
遊びながらも体調の変化に気を配り、こまめに着替えや休憩を促す。
水遊びやプール時は安全管理を徹底し、一人ひとりに合った対応をする。
◎人間関係
友達と一緒に活動する楽しさを味わい、簡単なルールを理解し始める。
友達の存在を意識し、共感したり譲り合ったりする経験を重ねる。
保育者の配慮
友達同士のやりとりを温かく見守り、トラブル時には気持ちに寄り添って支援する。
一緒に楽しめた喜びを大いに共有し、関係を育む。
◎環境
夏の自然(虫、水、草花など)に触れ、好奇心を広げる。
身近な環境の変化(天気、音、色など)に気づく。
保育者の配慮
自然物に触れる機会をたくさん作り、興味を深められるよう導く。
危険なものからはしっかり守りながら、豊かな発見を楽しめるようにする。
◎言葉
自分の気持ちや発見を、簡単な言葉で伝えようとする。
友達や保育者とのやりとりを通して、言葉のやりとりを楽しむ。
保育者の配慮
子どもの発した言葉をしっかり受け止め、さらに言葉を引き出す関わりを心がける。
話し合いや簡単なやりとりの楽しさを一緒に味わう。
◎表現
音楽やリズムに合わせて体を動かしたり、自由な発想で絵を描いたりする。
夏の素材(水、砂、泡など)を使った感触遊びを楽しむ。
保育者の配慮
子どもの自由な表現を受け止め、「楽しいね」「面白いね」と共感する。
感触遊びでは無理に触れさせず、興味を引き出すようにサポートする。
◎食育
夏野菜や果物(とうもろこし、スイカなど)に親しみ、食への関心を深める。
暑い時期の食事や水分補給の大切さを体験的に知る。
保育者の配慮
旬の食材を紹介したり、一緒に味わったりする機会を作る。
「水分をとろうね」と声かけしながら、健康的な食生活をサポートする。
◎家庭との連携
夏ならではの活動(水遊び、プール遊び)に関する情報共有を密に行う。
体調管理や生活リズムについて、家庭と連携して支える。
◎職員間の連携
体調や疲れ具合を細かく観察し、必要に応じて職員間で柔軟に対応する。
夏の行事や活動を安全に行えるよう、共通理解を深める。
◎異年齢保育
年上の子どもと関わる中で、新しい遊び方やルールを学ぶ。
年下の子どもに対して思いやりの気持ちが芽生える。
保育者の配慮
異年齢での関わりを自然に生み出し、年齢差に応じた援助を行う。
◎長時間保育の配慮
夕方は静かな遊びや絵本の時間を取り入れ、疲れを癒せるようにする。
気温や体調に配慮しながら、無理のない過ごし方を心がける。
【第3期(10月〜12月)】
◎ねらい
秋や冬の自然の変化に気づき、興味や関心を広げる。
自分の思いを伝えながら、友達との関係を深める。
◎生命
気温の変化に合わせた衣服の調節を覚え、健康に過ごす力を育てる。
感染症予防(手洗い、うがい)に興味を持ち、生活に取り入れる。
保育者の配慮
気温や子どもの様子に応じて、衣服の調節をこまめに声かけする。
手洗いやうがいを遊び感覚で取り入れ、楽しく習慣化できるようにする。
◎情緒
秋や冬の行事に参加し、期待感や達成感を味わう。
友達とのやりとりを楽しみ、喜びや悔しさを経験しながら心を育む。
保育者の配慮
行事の中で子ども一人ひとりの気持ちに寄り添い、成功体験を大切にする。
感情が大きく揺れ動く場面でも、受け止め共感することで安心感を与える。
◎5領域
◎健康
寒さに負けずに体を動かして遊び、基礎体力を養う。
風邪予防のために、体を温める習慣を意識する。
保育者の配慮
寒い時期でも戸外遊びを取り入れ、楽しく体を動かせる環境を整える。
防寒や健康管理について、子どもにわかりやすく伝える。
◎人間関係
簡単なルールを理解しながら、友達と一緒に遊ぶ楽しさを味わう。
困ったときに保育者や友達に助けを求められるようになる。
保育者の配慮
遊びの中でルールや順番を楽しく知らせ、成功体験へつなげる。
困った気持ちを代弁し、安心して助けを求められる環境をつくる。
◎環境
落ち葉や木の実など、秋ならではの自然物に触れて遊ぶ。
季節の変化(木々の色づき、空気の冷たさ)に気づき、感性を豊かにする。
保育者の配慮
季節を感じられる散歩や自然遊びを多く取り入れる。
自然物に触れる中で安全に配慮しながら、驚きや発見を共有する。
◎言葉
秋や冬の行事、自然に触れる中で、新しい言葉に興味を持つ。
自分の気持ちを言葉で伝えようとする意欲を育てる。
保育者の配慮
子どもの言葉を丁寧に聞き返し、やりとりを広げる工夫をする。
新しい言葉や表現を遊びの中で自然に取り入れる。
◎表現
秋の自然物を使った製作活動を楽しむ。
音楽やリズムに合わせて体を動かし、自由に表現する喜びを味わう。
保育者の配慮
作品づくりの過程を大切にし、自由な発想を受け止める。
音楽や表現活動に、子どもの気持ちが乗るように環境を工夫する。
◎食育
秋の味覚(さつまいも、りんごなど)に親しみ、季節の食材を楽しむ。
「食べることが体を元気にする」感覚を育てる。
保育者の配慮
旬の食材に触れる体験(クッキング、試食など)を取り入れる。
食べる喜びを一緒に味わい、無理強いせず楽しめる雰囲気を大切にする。
◎家庭との連携
体調管理(衣服調節、感染症対策)について、こまめに情報を共有する。
家庭でも季節行事に親しめるよう、園での活動を伝える。
◎職員間の連携
子どもの健康状態や情緒面の変化を細かく共有し、柔軟に対応する。
行事に向けて職員間で計画・役割分担を明確にし、連携を深める。
◎異年齢保育
異年齢の友達と関わる中で、模倣や思いやりの気持ちを育む。
年上の子どもに憧れる気持ちを大切にし、意欲につなげる。
保育者の配慮
異年齢での交流を楽しく体験できる機会をつくる。
それぞれの発達段階に合わせて無理なく関われるよう支援する。
◎長時間保育の配慮
一日のリズムを大切にし、静かに過ごす時間と活動する時間のメリハリをつける。
帰りの時間に向けて、心身ともにリラックスできるようにする。
【第4期(1月〜3月)】
◎ねらい
一年間の成長を振り返りながら、自信を持って生活や遊びに取り組む。
進級への期待を持ち、身の回りのことに意欲的に挑戦する。
◎生命
寒い季節でも体調管理に気をつけ、元気に過ごす力を育てる。
身の回りのこと(衣服の着脱、手洗いなど)を自分でしようとする意欲を持つ。
保育者の配慮
気温や体調に応じた過ごし方をこまめにサポートし、無理なく健康維持できるよう配慮する。
できることを温かく見守り、子ども自身の達成感を味わえるよう援助する。
◎情緒
進級に向けての期待や不安を受け止め、安心感を持って過ごせるようにする。
「できた!」という達成感を積み重ね、自信につなげる。
保育者の配慮
進級についてさりげなく話題にし、楽しみながらイメージを広げられるようにする。
不安や戸惑いが見られる子には、丁寧に寄り添いながら小さな成功体験を支える。
◎5領域
◎健康
冬ならではの遊び(雪遊び、室内運動遊びなど)を楽しみ、体を動かす心地よさを味わう。
寒い中でも元気に遊べる体づくりを意識する。
保育者の配慮
室内でも十分に体を動かせる遊びを工夫し、体力の維持を図る。
寒さによる体調変化に留意し、無理なく遊びに取り組めるよう配慮する。
◎人間関係
友達と一緒に活動する中で、ルールや順番を意識できるようになる。
簡単な集団遊びを楽しみ、仲間意識を育てる。
保育者の配慮
活動の中で自然にルールを知らせ、友達と協力する楽しさを感じられるよう支える。
トラブル時にはすぐに介入せず、必要に応じてそっとサポートする。
◎環境
冬の自然(霜柱、氷、木の葉など)に触れ、季節ならではの発見を楽しむ。
身近な環境に興味を持ち、探求しようとする気持ちを育てる。
保育者の配慮
冬の自然に触れられる機会を意識的に設け、子どもの気づきを大切に受け止める。
安全に留意しながら、探究心を育む活動を展開する。
◎言葉
日常の中での経験を、簡単な言葉や文章で伝えようとする。
友達や保育者とのやりとりを楽しみ、会話を広げる力を育てる。
保育者の配慮
子どもの言葉を丁寧に拾い、さらに広げる応答を心がける。
楽しいやりとりを通して、言葉を使う喜びを味わえるようにする。
◎表現
身近な素材や道具を使って自由に表現する楽しさを味わう。
音楽に合わせて表現したり、イメージを膨らませた遊びを楽しむ。
保育者の配慮
自由な発想を尊重し、「つくる・表す」楽しさにじっくり関われるよう支援する。
一人ひとりの表現を受け止め、ありのまま認める姿勢を大切にする。
◎食育
冬の食材や郷土料理に親しみ、食文化への興味を育てる。
「食べることの大切さ」を理解し、感謝の気持ちを持つきっかけをつくる。
保育者の配慮
行事食や季節の料理を紹介し、食への関心を高める。
食材の由来や調理過程をわかりやすく伝え、食に興味を持てるようにする。
◎家庭との連携
進級に向けた子どもの成長や変化を共有し、安心して次のステップへ進めるようにする。
家庭でも子どもが「できるようになったこと」を喜び合えるよう支援する。
◎職員間の連携
子どもの成長を職員間で細かく共有し、個々に応じた進級支援を行う。
一人ひとりの思いに寄り添った対応ができるよう、チームで連携を図る。
◎異年齢保育
年下の子への思いやり、年上の子への憧れの気持ちを育む。
異年齢の子どもたちと関わる中で、自信と社会性を育てる。
保育者の配慮
異年齢との関わりを安心して楽しめる環境を整える。
一人ひとりの経験や成長を大切にしながら、自然な交流を支援する。
◎長時間保育の配慮
年度末に向け、心身ともにゆったりと過ごせる時間を意識する。
子ども一人ひとりが安心して過ごせる環境づくりを心がける。
この1年を通して、子どもたちは「できた」「たのしい」と感じる経験を積み重ねながら、自信や自己肯定感を育んでいきます。日々の生活の中で保育者に受けとめてもらう安心感を基盤に、自分の気持ちを少しずつ言葉や行動で表現できるようになっていきます。
また、友達の存在に気づき、一緒に遊ぶ楽しさや、他者と関わる中でのルールや思いやりの芽も育ち始めます。保育者は、子どもたち一人ひとりのペースを大切にしながら、心身の発達に応じた関わりを心がけ、豊かな生活と遊びの場を通して、健やかな成長を支えていきます。


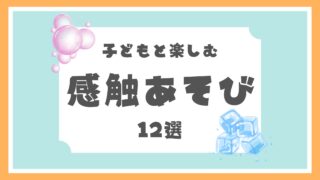
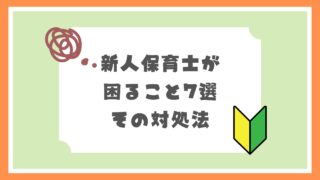
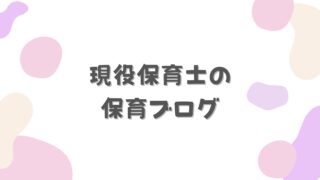



コメント