年長児の1年は、園生活の集大成ともいえる大切な時期です。これまでの経験を土台に、「自分で考えて行動する力」や「仲間と協力する力」をさらに深め、小学校への期待をふくらませながら心身ともに大きく成長していきます。
前半期は、新しい環境や友達との関わりの中で、自分の役割を少しずつ意識しながら、年長児としての自覚や主体性を育んでいきます。中盤には、様々な行事や活動を通して、仲間と力を合わせる喜びや達成感を味わい、困難にも前向きに取り組む姿が見られるようになります。終盤には、園で過ごす日々を振り返りながら、就学に向けて期待と自信をもって次のステップへと進めるよう、心の準備を整えていきます。
私たち保育者は、一人ひとりの成長に寄り添いながら、子どもが自分らしさを発揮し、自信をもって歩んでいけるような保育環境を整え、保護者や職員との連携を大切にして支援していきます。
◎1年のねらい
自分で考え、行動する力を育て、集団の中で自信をもって生活する。
友達と力を合わせる楽しさを知り、小学校への期待を膨らませる。
【第1期(4月〜6月)】
◎ねらい
新しい環境や友達に親しみ、年長児としての自覚を持ち始める。
生活習慣を見直し、より主体的に行動する力を育てる。
◎生命
自分の健康や安全に気を配りながら生活する。
基本的な生活習慣を安定させ、体調を整える。
保育者の配慮
健康や安全について子ども自身が意識できるよう丁寧に伝える。
一人ひとりの生活リズムや体調に合わせて、無理のない支援を行う。
◎情緒
年長児としての役割に喜びや自信を感じる。
友達との関わりの中で、自分の気持ちを落ち着いて伝えることができる。
保育者の配慮
年長として期待しすぎず、子ども自身のペースを大切にする。
成功体験を積み重ね、自信を持てるように具体的に認める。
◎5領域
◎健康
身体を動かす楽しさを感じ、体力づくりに取り組む。
自分の健康を意識して、必要な行動を考える力を育てる。
保育者の配慮
活動と休息のバランスをとり、無理なく取り組めるよう配慮する。
身体を動かす喜びが感じられる遊びを取り入れる。
◎人間関係
友達との関わりの中で、相手の気持ちを考えながら行動する。
トラブルがあっても、自分たちで話し合って解決しようとする力を育む。
保育者の配慮
子どもたちの話し合いを温かく見守り、必要に応じてサポートする。
友達関係の中で自信を持てるよう、成功体験を積ませる。
◎環境
身近な自然や社会に関心を持ち、探究心を深める。
物事に対して「どうして?」「やってみたい!」という気持ちを大切にする。
保育者の配慮
子どもの興味に寄り添い、調べたり試したりする体験をサポートする。
季節や行事に関連する活動を取り入れ、体験の幅を広げる。
◎言葉
自分の考えや気持ちを相手にわかりやすく伝えようとする。
友達との話し合いを通して、意見を交換しながら活動する。
保育者の配慮
子どもの発言を肯定的に受け止め、自分の意見を言える自信を育む。
言葉で解決できたときは大いに認め、達成感につなげる。
◎表現
自分の感じたことや考えたことを、様々な方法で表現する。
友達と協力して表現活動に取り組み、達成感を味わう。
保育者の配慮
表現活動を通して自己表現の喜びを味わえるよう支援する。
一人ひとりの発想を尊重し、自由な表現を大切にする。
◎食育
自分の体に必要な栄養や食事の大切さを知る。
旬の食材や行事食に関心を持ち、楽しく食事をする。
保育者の配慮
食材の話や食事作りの体験を取り入れ、興味を広げる。
「食べることは体をつくること」という意識を楽しく伝える。
◎家庭との連携
年長児としての成長を家庭と共有し、期待と支援を依頼する。
生活リズムや基本的生活習慣について、家庭と連携して整える。
◎職員間の連携
子どもの成長の過程を共有し、個別の課題に応じた支援を行う。
小学校へのスムーズな移行を見据え、園全体でサポートする。
◎異年齢保育
年下児に優しく接し、思いやりやリーダーシップを育てる。
異年齢の交流を通して、自分の役割に自信と責任感を持つ。
保育者の配慮
年長児としての負担を感じすぎないよう、自然なかかわりを大切にする。
◎長時間保育の配慮
活動量や刺激が多くなりがちな時期でも、心と体を休める時間を確保する。
安心できる環境でリラックスして過ごせるように配慮する。
【第2期(7月〜9月)】
◎ねらい
夏の自然に親しみながら、体力を養う。
友達との関わりを深め、協力して物事に取り組む喜びを味わう。
◎生命
暑さや疲れに気づき、自分の体調を考えながら生活する。
休息や水分補給など、健康管理に自ら取り組む。
保育者の配慮
体調の変化に敏感に気づき、声をかけてサポートする。
無理のない活動計画を立て、体調を最優先に考える。
◎情緒
楽しいことや困ったことを友達と共有しながら、心を通わせる。
集団の中でも自分らしさを大切にし、安心して過ごす。
保育者の配慮
感情の揺れを受け止め、子どもの思いに寄り添う。
嬉しい気持ちや頑張ったことを一緒に喜び、自信につなげる。
◎5領域
◎健康
夏ならではの遊び(プール遊び、水遊びなど)を存分に楽しむ。
活動後の休息や水分補給を意識し、自分で調整できるようになる。
保育者の配慮
暑さや疲れに配慮しながら、安全に活動できる環境を整える。
活動と休息のバランスを大切にし、無理なく楽しめるよう支援する。
◎人間関係
友達と助け合ったり、意見を出し合ったりしながら活動する。
異なる考えを認め合う経験を積み、相手を尊重する心を育む。
保育者の配慮
話し合いの場を設け、互いの考えを伝え合う機会を増やす。
うまくいかない時も認め、次につなげる声かけを心がける。
◎環境
夏の自然(昆虫、水辺の生き物、植物など)に興味をもつ。
観察や調べ学習を通して、自然の不思議さや命の大切さに気づく。
保育者の配慮
子どもの「なぜ?」を大切にし、一緒に調べたり考えたりする。
実際に見たり触れたりする体験を多く取り入れる。
◎言葉
夏の体験を言葉で表現したり、友達に伝えたりする。
自分の思いや考えを、場面に応じた言葉で伝える力を育む。
保育者の配慮
自由に話せる時間や場を設け、伝える楽しさを感じさせる。
相手の話を聞く姿勢も育て、双方向のコミュニケーションを支援する。
◎表現
夏の自然や体験を、絵画や製作、音楽、リズム遊びなどで表現する。
友達と一緒に表現する楽しさを感じ、共同制作にも挑戦する。
保育者の配慮
一人ひとりの感じ方や表現を大切にし、自由に表現できる環境を整える。
「面白いね」「素敵だね」と共感する声かけを大切にする。
◎食育
夏野菜や旬の食べ物に親しみ、食べ物への興味を深める。
水分補給や食事の大切さを意識し、健康な生活につなげる。
保育者の配慮
夏ならではの食材に触れる機会を作り、楽しく食育を行う。
食事の大切さをわかりやすく伝え、食べる意欲を育てる。
◎家庭との連携
体調管理や生活リズムについて、家庭と情報共有を密にする。
夏ならではの体験(旅行、自然遊びなど)を家庭でも楽しめるよう支援する。
◎職員間の連携
体調や情緒面の変化を細やかに共有し、必要に応じて対応する。
行事や活動の際、安全面を最優先に職員間で連携を深める。
◎異年齢保育
年下の子どもたちに対して、思いやりのある行動を示す。
異年齢とのかかわりを通じて、リーダーシップを自然に発揮する。
保育者の配慮
年長児らしさを求めすぎず、無理なく自然体でかかわれるよう配慮する。
◎長時間保育の配慮
暑さで疲れが出やすい時期なので、十分な休息を取り入れる。
家庭的な雰囲気の中で安心して過ごせるよう環境を整える。
【第3期(10月〜12月)】
◎ねらい
身の回りのことに主体的に取り組み、達成感を味わう。
仲間と協力しながら、共通の目的に向かって活動する楽しさを感じる。
◎生命
寒暖差に気を配りながら、衣服の調節や体調管理を意識する。
健康に過ごすために自分で考え、行動できるようになる。
保育者の配慮
気温や体調の変化に合わせて、必要な支援や声かけを行う。
子ども自身が気づき、自分で対応できる力を育てる。
◎情緒
仲間との関わりの中で、自分の感情を調整しながら過ごす。
挑戦する気持ちを支え、自信や達成感を積み重ねる。
保育者の配慮
葛藤や悩みに寄り添い、気持ちの整理を手助けする。
努力や成長をしっかり認め、自己肯定感を高める関わりを大切にする。
◎5領域
◎健康
運動会や戸外遊びを通して、体を動かす心地よさを味わう。
活動後の休息や栄養補給を自分で意識できるようになる。
保育者の配慮
達成感を味わえるように個々の努力を認め、励ます。
疲れやすい時期には無理をさせず、健康管理を優先する。
◎人間関係
仲間と目標を共有し、協力して取り組む喜びを味わう。
相手の思いや立場を考えて行動する力を育てる。
保育者の配慮
チームでの取り組みを楽しめるよう、ポジティブな声かけを心がける。
トラブルが起きた時は、話し合いを通して解決できる力を支える。
◎環境
秋の自然(落ち葉、木の実、生き物など)に触れ、季節の変化に気づく。
素材や自然現象に興味をもって探求する意欲を育む。
保育者の配慮
自然に触れる機会を多く作り、子どもの「発見」を大切にする。
環境を守る意識や、命を大切にする心を育む言葉がけを行う。
◎言葉
自分の思いを文章や物語にして表現する楽しさを味わう。
友達の話にも興味をもち、聞く力・伝える力を伸ばす。
保育者の配慮
話す楽しさ、聞く面白さを感じられる場面をたくさん用意する。
子どもたちの表現を受け止め、さらに広げられるよう関わる。
◎表現
運動会や発表会などで、自分を表現する喜びを味わう。
友達と一緒に創り上げる活動を通して、協働する楽しさを知る。
保育者の配慮
結果ではなく、過程や頑張りをしっかり認めて励ます。
表現することの楽しさや達成感を味わえるような場づくりを心がける。
◎食育
秋の味覚(果物、根菜類など)に触れ、季節を感じながら食べる楽しさを味わう。
食材への興味を深め、栄養の大切さにも気づく。
保育者の配慮
食べ物が育つ過程や、旬の味わいについて楽しく伝える。
好き嫌いに無理に働きかけず、興味関心を広げるきっかけをつくる。
◎家庭との連携
運動会、発表会など行事を通して、子どもの成長を一緒に喜び合う。
家庭でも健康管理や生活リズムを整える大切さを共有する。
◎職員間の連携
行事や活動の進行状況を共有し、柔軟にサポートし合う。
子どもの変化や体調を見逃さず、迅速に連携して対応する。
◎異年齢保育
異年齢の子どもたちに優しく接し、自らお手本となる姿を見せる。
年下の子どもを支えることで、リーダーシップと優しさを育む。
保育者の配慮
「助ける」「見守る」役割を押しつけず、自然に関われるよう配慮する。
◎長時間保育の配慮
疲れがたまりやすい時期なので、ゆったりとした時間を大切にする。
安心して過ごせる空間作りや、気持ちのリセットができる工夫を行う。
【第4期(1月〜3月)】
◎ねらい
これまでの経験を活かし、自信をもって活動する。
小学校への期待を膨らませ、就学に向けて心身の準備を整える。
◎生命
冬の寒さに負けず、健康に気をつけて過ごす。
自分の体調や生活リズムを振り返り、必要な調整ができるようになる。
保育者の配慮
感染症予防や体調管理について、日々の生活の中で意識づけを行う。
疲れや不調を早期に察知し、無理をさせないように配慮する。
◎情緒
園生活の終わりを意識しながら、友達や保育者との時間を大切にする。
期待と不安が入り混じる中で、心の安定を図りながら前向きに進もうとする。
保育者の配慮
別れへの不安や寂しさに寄り添い、十分に甘えられる時間を保障する。
小学校生活への期待を育み、安心して進学できるよう支える。
◎5領域
◎健康
寒い季節でも体を動かす習慣を大切にし、健康な体づくりを意識する。
生活リズムを整え、規則正しい生活を意識できるようにする。
保育者の配慮
冬でも楽しく体を動かせる遊びや活動を工夫する。
疲れが出やすい時期は、無理をせず適度に休息を取るよう促す。
◎人間関係
友達との関係を深め、互いを認め合いながら過ごす。
卒園を意識しながら、大切な仲間との絆を感じる。
保育者の配慮
子ども同士のつながりを温かく見守り、思い出づくりを支援する。
トラブルがあっても仲直りできるようサポートし、自信につなげる。
◎環境
冬の自然(霜、氷、冬の生き物など)に触れ、季節の変化に気づく。
身の回りの環境への関心を深め、大切にする心を育む。
保育者の配慮
冬ならではの自然現象に親しみ、発見の喜びを味わえる体験を提供する。
命や自然への思いやりを育てる機会を大切にする。
◎言葉
自分の経験や思いを、豊かな言葉で伝える力を育てる。
卒園や進学に向けて、思いを言葉にして整理する。
保育者の配慮
話す・聞く体験を積み重ね、自信をもって伝える機会を作る。
子どもの表現を丁寧に受け止め、肯定的に返すことで意欲を支える。
◎表現
卒園制作や発表などを通して、自分らしく表現する喜びを味わう。
友達と協力して一つのものを作り上げる達成感を味わう。
保育者の配慮
過程を大切にしながら、個々の思いや表現を尊重する。
「できた!」という喜びを共に味わい、自信につなげる。
◎食育
お正月の食文化や、冬の旬の食材に触れ、食への興味関心を広げる。
小学校に向けて、食事のマナーや栄養バランスを意識できるようにする。
保育者の配慮
行事食を楽しく紹介し、日本の食文化への親しみを育む。
食事の基本的なマナーや、食べることへの感謝を伝える。
◎家庭との連携
就学に向けた生活習慣の見直しや、心の準備について情報を共有する。
園での姿や成長を伝え、家庭でも安心して送り出せるよう支える。
◎職員間の連携
卒園に向けた活動や行事の進行をスムーズに進めるため、密に情報共有を行う。
子どもの小さな変化も見逃さず、丁寧にサポートする。
◎異年齢保育
年下の子どもたちへの思いやりや優しさを自然に表現できるようにする。
自分が憧れの存在となる喜びや自信を味わう。
保育者の配慮
年上児としての役割を押しつけず、自然な関わりを支援する。
◎長時間保育の配慮
卒園に向けた慌ただしさの中でも、一人ひとりが安心して過ごせるよう配慮する。
疲れがたまらないよう、リラックスできる時間を大切にする。
◎まとめ
年長児の1年間は、就学に向けて心と体の土台を築く大切な時期です。子どもたちは、自分で考え行動する力を育みながら、仲間と協力する楽しさや達成感を経験し、少しずつ小学生になる準備を整えていきます。
各期を通じて、季節の変化や行事、日々の生活の中で様々な経験を重ねることで、心身の成長が促されます。自分自身の気持ちに気づき、相手の思いにも目を向けられるようになる姿は、集団の中で過ごす中で少しずつ育まれていきます。
保育者はその歩みを温かく見守りながら、一人ひとりの成長段階に応じた援助を行い、安心して挑戦できる環境を整えることが大切です。また、家庭や職員間との連携を密にし、園全体で子どもたちの就学への移行を支えていく姿勢が求められます。
年長児期は、子どもにとって大きな自信と誇りを育む時期であり、人生の中でも特別な1年間です。この時期に感じた「できた!」「わかってもらえた!」「楽しかった!」という体験が、これからの学びの土台となり、より良い成長へとつながっていきます。


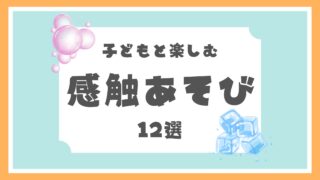
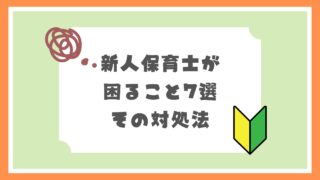
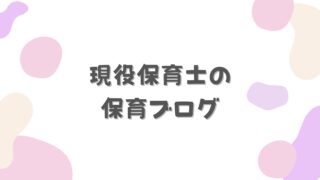


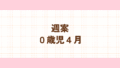
コメント