4歳児は、友達との関わりがますます活発になり、社会性が大きく育つ時期です。自分の気持ちを言葉で伝えたり、相手の思いを受け止めたりしながら、集団の中でのルールや役割を理解しようとする姿が見られるようになります。
遊びの幅も広がり、ごっこ遊びやルールのある遊びなど、友達と協力し合って楽しむ中で、想像力や思考力、協調性が育まれていきます。失敗や衝突も経験しながら、「どうしたらうまくいくか」「こうしてみよう」と考える力も少しずつ芽生えてきます。
この1年は、友達との関係を深めながら、自分の気持ちに折り合いをつけたり、相手を思いやったりする経験を積み重ねていく大切な時期です。保育者は、一人ひとりの思いや育ちに丁寧に寄り添いながら、安心して自分を出せる関係や環境づくりを心がけていきます。
◎1年のねらい
友達や保育者との関わりを深めながら、自分の気持ちを伝えたり、相手を思いやる心を育てる。
生活習慣を確立し、自分でできることに自信を持ち、挑戦する気持ちを育む。
【第1期(4月〜6月)】
◎ねらい
新しい環境に慣れ、保育者や友達との信頼関係を築く。
基本的な生活習慣(食事・排泄・着脱など)を身につけ、自分で行おうとする意欲を育てる。
◎生命
新しい生活リズムに慣れ、健康に過ごす。
生活の中で自分の体に関心を持ち、無理なく自分でできることを増やす。
保育者の配慮
一人ひとりの生活リズムや体調を細かく把握し、安心して過ごせるようにする。
「できた!」という達成感を大切にし、無理なく挑戦できる環境を整える。
◎情緒
新しい集団生活に安心感を持ち、保育者や友達との信頼関係を築く。
自分の気持ちを素直に表現し、受け止めてもらうことで情緒の安定を図る。
保育者の配慮
子どもの気持ちを丁寧に受け止め、共感しながら安心感を与える。
戸惑いや不安を感じる子どもには特に寄り添い、焦らず心を開けるよう支援する。
◎5領域
◎健康
新しい生活リズムに慣れ、元気に活動できる体を作る。
自分で衣服の着脱や排泄の自立を目指し、達成感を味わう。
保育者の配慮
成功体験を積み重ねられるよう、小さなできたを認めて励ます。
無理な自立を押し付けず、個々のペースに合わせて支援する。
◎人間関係
友達と一緒に遊ぶ楽しさを感じ、相手の気持ちを少しずつ理解しようとする。
簡単なルールを守りながら、みんなで活動する経験を重ねる。
保育者の配慮
友達との関わりを温かく見守りながら、トラブル時は仲立ちをして関係を築けるようサポートする。
活動の中で協力や思いやりを育めるような声かけを行う。
◎環境
新しい園生活や身の回りの環境に興味を持ち、自分なりに関わる。
園庭や園内の自然に触れ、季節の変化を楽しむ。
保育者の配慮
子どもたちが自発的に探索・発見できるよう、環境を工夫する。
自然や生き物に触れる機会を増やし、驚きや感動を共有する。
◎言葉
自分の思いや考えを言葉で伝えようとする。
友達とのやりとりの中で、聞く力・話す力を育てる。
保育者の配慮
子どもの発言をしっかり受け止め、肯定的に返すことで、表現する意欲を育てる。
友達同士の会話を広げられるような援助をする。
◎表現
歌やリズム遊び、絵画・製作を通して、自分の感じたことを自由に表現する。
身振りや表情、体の動きを使って自分を表現する楽しさを味わう。
保育者の配慮
結果より過程を大切にし、子どもの「やってみたい!」を引き出す環境を整える。
表現活動の楽しさを一緒に味わいながら、自己肯定感を育てる。
◎食育
春・初夏の旬の食材に親しみ、食べることへの興味を広げる。
食事の際のマナーを知り、楽しく食べる習慣を身につける。
保育者の配慮
旬の食材や行事食について話題にし、興味を引き出す。
食事中の姿勢や箸の使い方も優しく促しながら、楽しく食事ができる雰囲気を作る。
◎家庭との連携
園での新しい生活リズムや子どもの様子をこまめに伝え、安心してもらう。
生活習慣や健康管理について家庭と情報共有をし、協力して支えていく。
◎職員間の連携
子ども一人ひとりの新しい環境への適応状況を共有し、適切な支援を行う。
小さな変化も見逃さず、連携して対応する。
◎異年齢保育
年下の子どもへの思いやりや、年上の子への憧れの気持ちを育む。
異年齢での遊びや活動を通して、自然な関わりを大切にする。
保育者の配慮
異年齢交流の場面を意識的に設け、それぞれの役割を楽しめるよう支援する。
◎長時間保育の配慮
一人ひとりの疲れに配慮し、安心して休息できる時間と空間を整える。
活動と休息のバランスをとり、リズムよく過ごせるようにする。
【第2期(7月〜9月)】
◎ねらい
暑さに負けず健康に過ごし、夏ならではの遊びを楽しむ。
友達との関わりを深めながら、自分の思いや相手の気持ちに気づき、伝え合おうとする。
◎生命
暑さに負けず、自分の体調を意識しながら元気に過ごす。
夏ならではの体験(プール遊び、水遊び)を通して、体を動かす楽しさを味わう。
保育者の配慮
子どもたちの体調の変化を細かく観察し、無理のない活動を心がける。
こまめな水分補給や休息を促しながら、健康を守る支援を行う。
◎情緒
夏の行事や遊びを通して、達成感や喜びを感じる。
友達との関わりの中で、自分の思いや考えを伝える経験を重ねる。
保育者の配慮
子どもたちの小さな成長や挑戦を見逃さず、一緒に喜び合う。
友達とのトラブルが起きた時には気持ちに寄り添い、安心して関われるよう支援する。
◎5領域
◎健康
夏の暑さに負けず、健康的な生活習慣(早寝早起き、食事、水分補給)を意識する。
プールや水遊びを通して、体を十分に動かし、体力を養う。
保育者の配慮
活動後のクールダウンや休息を大切にし、無理をさせないよう配慮する。
生活リズムの乱れがないか家庭と連携しながら支援する。
◎人間関係
夏祭りごっこやグループ活動など、共同で取り組む楽しさを味わう。
友達との違いを認め合いながら、協力して遊びを広げる。
保育者の配慮
協同作業の中で、子どもたち一人ひとりの役割を大切にする。
トラブルがあった際も子ども同士で話し合う機会を作り、見守りながら支援する。
◎環境
夏ならではの自然現象(セミの鳴き声、ひまわりの成長、夕立など)に興味を持つ。
水や砂、自然素材を使った遊びを楽しみ、感覚を豊かにする。
保育者の配慮
身近な自然を題材にして、自由に触れたり遊んだりできる環境を整える。
子どもの発見を一緒に楽しみ、好奇心を広げる声かけを心がける。
◎言葉
夏の遊びや行事を通して、楽しかったことを言葉で伝え合う。
友達や保育者との会話を楽しみ、伝える力・聞く力を育てる。
保育者の配慮
子ども同士の会話を促し、発表する楽しさを感じられる機会を作る。
発言を急かさず、待つ姿勢を大切にする。
◎表現
水遊びや製作、夏祭りごっこなど、夏の素材を使って自由に表現する。
リズム遊びやダンスを通して、体全体を使った表現を楽しむ。
保育者の配慮
表現方法に正解を求めず、子どもの自由な発想を受け止める。
素材や表現活動に親しみやすい環境を整え、「やってみたい」を引き出す。
◎食育
夏の野菜や果物に親しみ、旬の食材を知る。
食事の大切さや水分補給の必要性を学び、健康意識を高める。
保育者の配慮
食材の話をすることで興味を引き出し、食への関心を深める。
無理に食べさせず、楽しい食事の時間になるよう配慮する。
◎家庭との連携
夏ならではの体調変化や生活リズムについて情報を共有する。
園での活動や行事を家庭にも伝え、一緒に成長を喜び合う。
◎職員間の連携
水遊びやプール遊びにおける安全管理を徹底し、常に連携して子どもたちを見守る。
一人ひとりの小さな変化にも気づき、柔軟に対応する。
◎異年齢保育
夏祭りごっこなど、異年齢の友達と一緒に行事を楽しむ中で、思いやりや協力する心を育てる。
年下の子に優しく接する経験を重ねる。
保育者の配慮
異年齢交流で互いに学び合えるよう、自然な関わりを大切にする。
◎長時間保育の配慮
暑さで疲れが出やすい時期のため、活動と休息のバランスに十分配慮する。
落ち着いて休める環境を整え、安心して一日を過ごせるようにする。
【第3期(10月〜12月)】
◎ねらい
秋から冬への自然の変化に興味を持ち、季節を感じながら生活する。
友達との関わりを深め、互いに思いやりをもって過ごそうとする。
◎生命
気温の変化に気をつけながら、健康に過ごす。
手洗い・うがいなど、感染症予防の習慣を身につける。
保育者の配慮
衣服の調節や体調確認をこまめに行い、健康を守る支援をする。
感染症流行時は、子どもたちにわかりやすく予防行動を伝える。
◎情緒
運動会や発表会に向けて、挑戦する気持ちや達成感を味わう。
友達と協力する中で、喜びや悔しさなどさまざまな感情を経験する。
保育者の配慮
挑戦する姿を温かく見守り、小さな努力や変化も積極的に認める。
気持ちが揺れる場面では丁寧に受け止め、安心できる関わりを大切にする。
◎5領域
◎健康
寒暖差の大きい時期でも、体を動かして元気に過ごす。
基本的な生活習慣(手洗い・うがい・衣服調節)を意識して行う。
保育者の配慮
運動あそびや戸外あそびを無理なく取り入れ、体力づくりを支える。
生活習慣が身につくよう、繰り返し丁寧に伝える。
◎人間関係
友達と役割を分担しながら、協力して一つの目標に向かう経験を重ねる。
互いに認め合い、励まし合う喜びを味わう。
保育者の配慮
活動の中で子ども同士が助け合う姿を温かく見守る。
葛藤が生まれた時には、解決に向かう力を育てられるよう支援する。
◎環境
秋の自然物(どんぐり、落ち葉など)を使った遊びや製作を楽しむ。
季節ごとの行事(運動会、ハロウィン、クリスマスなど)に親しむ。
保育者の配慮
自然物や行事の背景を子どもたちにわかりやすく伝える。
興味や発見を深められるよう、さまざまな素材や体験の場を用意する。
◎言葉
自分の思いや活動を言葉で表現し、友達や保育者に伝える楽しさを感じる。
相手の話を最後まで聞こうとする態度を育てる。
保育者の配慮
子どもの発言に耳を傾け、肯定的に受け止める。
話し合いや伝え合いの場を設け、言葉でやり取りする機会を増やす。
◎表現
運動会や発表会に向けて、表現する喜びや達成感を味わう。
音楽やリズム、劇あそびを通して、自由に表現する楽しさを広げる。
保育者の配慮
表現活動では「できた・できない」よりも、過程を大切に見守る。
子どもの個性を尊重し、思いを表現できたことを一緒に喜ぶ。
◎食育
秋から冬の旬の食材を知り、興味を持つ。
食事を通して、体を温める食べ物や栄養への関心を深める。
保育者の配慮
旬の食材を取り上げ、実際に見たり触れたりする機会を作る。
楽しく食事をする中で、食材への親しみを育てる。
◎家庭との連携
衣服や健康管理について家庭と連携を取り、快適に園生活を送れるようにする。
運動会や発表会への取り組みを伝え、子どもたちの頑張りを共有する。
◎職員間の連携
行事に向けてチームで役割分担を明確にし、スムーズな連携を図る。
子どもたち一人ひとりの気持ちの変化を情報共有し、支援に活かす。
◎異年齢保育
年下の子どもたちに優しく接し、思いやりの心を育てる。
異年齢の友達との関わりの中で、自分の役割を意識して行動する。
保育者の配慮
異年齢交流では、年齢に応じた支援や声かけを行い、お互いに学び合える環境をつくる。
◎長時間保育の配慮
行事などで疲れやすい時期なので、ゆったりとした時間の流れを意識する。
落ち着けるコーナーや休息できるスペースを用意し、安心して過ごせるよう配慮する。
【第4期(1月〜3月)】
◎ねらい
1年間の生活や遊びを振り返り、自信や満足感をもって過ごす。
進級への期待を高めながら、生活リズムを整え、安定して過ごす。
◎生命
寒さに負けず、健康的に生活する。
生活リズムを整え、十分な休息と栄養を意識する。
保育者の配慮
室温や衣服の調節に配慮し、寒暖差による体調変化に注意する。
体調不良の早期発見と、必要に応じた休息の促しを行う。
◎情緒
1年間の成長を感じ、自信をもって進級に期待を膨らませる。
友達や保育者との別れに寂しさを感じながらも、前向きな気持ちを持つ。
保育者の配慮
子どもの頑張りや成長を具体的に認め、自己肯定感を育てる。
進級や別れに伴う不安な気持ちを丁寧に受け止め、寄り添う。
◎5領域
◎健康
規則正しい生活リズムを大切にし、心身ともに健やかに過ごす。
進級に向けて、身の回りのことを自分で行おうとする意欲を育てる。
保育者の配慮
生活リズムが乱れがちな時期でも、見通しをもたせて支援する。
子ども自身ができた喜びを味わえるような声かけを心がける。
◎人間関係
友達との関わりを振り返り、感謝の気持ちや思いやりの心を育てる。
小さなトラブルにも自分たちで考えて対応しようとする力を伸ばす。
保育者の配慮
友達との関わりを温かく見守り、気持ちを言葉で伝える手助けをする。
関係づくりの中での子どもの努力を受け止め、励ます。
◎環境
冬から春への季節の移り変わりを感じ、自然への興味を深める。
環境を大切にし、物や自然に愛着を持って関わる。
保育者の配慮
冬から春への変化を、五感を使って感じられる機会を作る。
自然や物を大切にする心を育むよう、丁寧にかかわる。
◎言葉
1年間の思い出を言葉で表現し、友達や保育者と共有する。
進級に向けた気持ちや期待を自分の言葉で伝える。
保育者の配慮
子どもの言葉に耳を傾け、成長を一緒に喜びながら受け止める。
安心して話せる雰囲気づくりを大切にする。
◎表現
一年間の活動を振り返り、思い出を製作や歌、劇などで表現する。
卒園や進級に向けて、自分の気持ちを自由に表現する。
保育者の配慮
表現活動では子どもの思いを尊重し、自由な発想を受け入れる。
表現を通して自信につながるよう、あたたかい声かけをする。
◎食育
冬の食材や行事食に親しみ、旬を楽しむ。
食べることへの感謝の気持ちを持つ。
保育者の配慮
旬の食材や行事食の意味をわかりやすく伝える。
食事の時間が楽しく、温かいものになるよう配慮する。
◎家庭との連携
1年間の子どもの成長を家庭と共有し、進級への期待を高めてもらう。
生活リズムや自立に向けた取り組みを伝え、家庭と連携を深める。
◎職員間の連携
子どもたちの成長や課題を共有し、進級に向けた支援に一貫性を持たせる。
一人ひとりの心情を把握し、安心して次のステップに進めるよう支える。
◎異年齢保育
年下の子どもたちをリードしながら、自分の成長を感じる。
異年齢の友達との交流の中で、思いやりや責任感を育む。
保育者の配慮
年上児としての役割を無理なく楽しめるよう、負担にならないように支援する。
◎長時間保育の配慮
年度末に向けて疲れが出やすいため、ゆったりと過ごす時間を大切にする。
安心して自分のペースで過ごせる環境づくりを行う。
4歳児は、友達との関係が深まる中で、自分なりの考えや気持ちを持ち、表現しようとする姿が多く見られるようになります。この時期にたくさんの対話や試行錯誤を経験することで、自己理解と他者理解の土台が育ちます。
1年間を通して、「自分で考えてやってみようとする力」や「友達と一緒に楽しむ力」が育まれるように、日々の遊びや生活の中にさまざまなきっかけをちりばめていきます。子どもが自信を持って挑戦し、仲間と共に喜びを分かち合えるよう、家庭との連携も大切にしながら支援していきます。


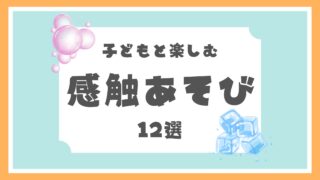
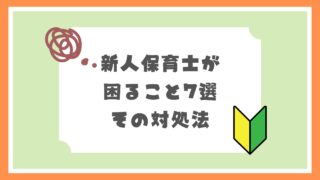
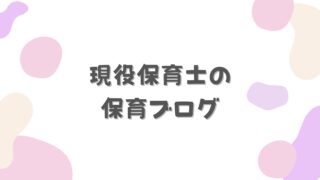



コメント