―保育士が実践する食事介助テクニック―
「またスプーンを投げちゃった…」「椅子に座っていられない」「ぜんぜん食べてくれない」
これは、ある1歳児クラスの昼食の風景でよくある場面です。私自身、食事介助に悩み、葛藤したことが何度もあります。
でも、ある日ふと気づいたんです。
“食べさせること”ばかりに気を取られて、“一緒に食べる楽しさ”を伝えられていなかったのかもしれないと。
私の園での経験から
私の働く園では、1歳児クラスでは一人ひとりの発達段階に合わせた個別対応が基本です。
ある子はスプーンの持ち方にこだわりがあり、ある子は一口ごとにお茶を飲みたがる。
最初は「みんな同じように食べさせなきゃ」と思っていたけれど、それが子どもにとっては“無理をさせていた”ことに後から気づきました。
そこで、職員同士で「その子がどこまで自分でできて、どこを援助すべきか」を共有するようになり、
声かけや食事の配置なども見直したところ、少しずつ「食べるのって楽しい!」という笑顔が増えていきました。
保護者の声と向き合って
保護者の方からも、
「家だと全然座って食べられないのに、保育園では食べてると聞いてびっくりしました」
「スプーンを持ちたがるようになって、自分で食べる意欲が出てきたんです」
という声をいただくことがあります。
その子の“園での食の姿”を保護者に共有することで、家庭での関わりにもつながっていく実感があります。
食事介助の目的は「完食」じゃない
大切なのは、“量を食べさせること”よりも、“食べることへのポジティブなイメージ”を育てること。
子ども自身が「自分で食べられた」「先生と一緒に食べて楽しかった」と思える経験を積み重ねていくことが、長い目で見て「食べる力」につながると感じています。
実際に効果があった 食事介助テクニック8選
1. 子どもと目線を合わせて「食べようね」とゆっくり声かけをする
▶ いきなりスプーンを口に運ぶよりも、まずは心の準備を整えてあげることが大切です。
目と目を合わせてやさしく声をかけると、「これからごはんだよ」という見通しが持てて、気持ちが落ち着きやすくなります。
2. スプーンやフォークは子どもが選べるように2〜3本準備
▶ 「自分で選ぶ」ことで、子どもにとっては食事が“自分の時間”になります。
道具へのこだわりが強い子には特に効果的で、抵抗感が減り、意欲的に食事へ向かうことができます。
3. ひと口サイズにする時は、子どもが飲み込みやすい形を意識する
▶ 子どもの咀嚼力や飲み込む力には個人差があります。
丸飲みしないように、やわらかさ・大きさ・形状をこまかく調整することで、安心して口に入れられるようになります。
4. 食べ始めを一緒にして「先生も食べてるよ」と見せる
▶ 「自分だけが食べさせられている」という感覚ではなく、「一緒に食べている」という空気感が大切です。
大人の行動をまねるのが上手な時期だからこそ、食べる姿を見せることが一番の導入になります。
5. 遊び食べには「食べ物はおもちゃじゃないよ」と一貫して伝える
▶ 食事の時間が“遊び”になってしまうと、食への意欲そのものが薄れてしまうこともあります。
ただ叱るのではなく、短く・穏やかに伝えて、食事の意味を少しずつ理解できるようにしていくことが大切です。
6. 席から離れようとしたら「あと一口食べたらおしまいにしようね」とゴールを伝える
▶ 何となく止められるより、「ここまで頑張ったら終わり」と見通しをもたせるほうが納得しやすいです。
自分で区切りを意識できるようになると、徐々に座っていられる時間も伸びていきます。
7. 食べない理由を探る(眠い・お腹が空いていない・集中力が切れている など)
▶ 無理に食べさせようとしても、子どもにとってはつらいだけになってしまうことがあります。
まずは「どうしてかな?」と気持ちや体調に寄り添って観察し、原因に応じた声かけや工夫をすることが大切です。
8. 「食べられたね!」「スプーンじょうずだったね」と結果より過程を褒める
▶ 子どもにとって「できた!」という体験は、何よりの自信につながります。
全部食べたかどうかよりも、「頑張ったこと」「工夫したこと」に目を向けて認めることで、食事への前向きな気持ちが育ちます
最後に
一人ひとりに合わせた食事介助は、時間も手間もかかります。
でも、「この子はこうやったら食べやすいんだよね」と気づけることが、私たち保育士にとっても大きなやりがいにつながります。
食事の時間が、子どもにとっても保育士にとっても“うれしい時間”になりますように。


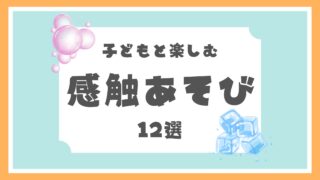
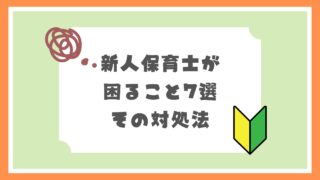
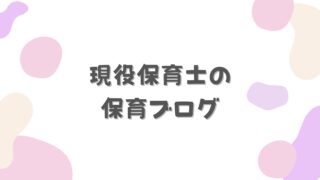
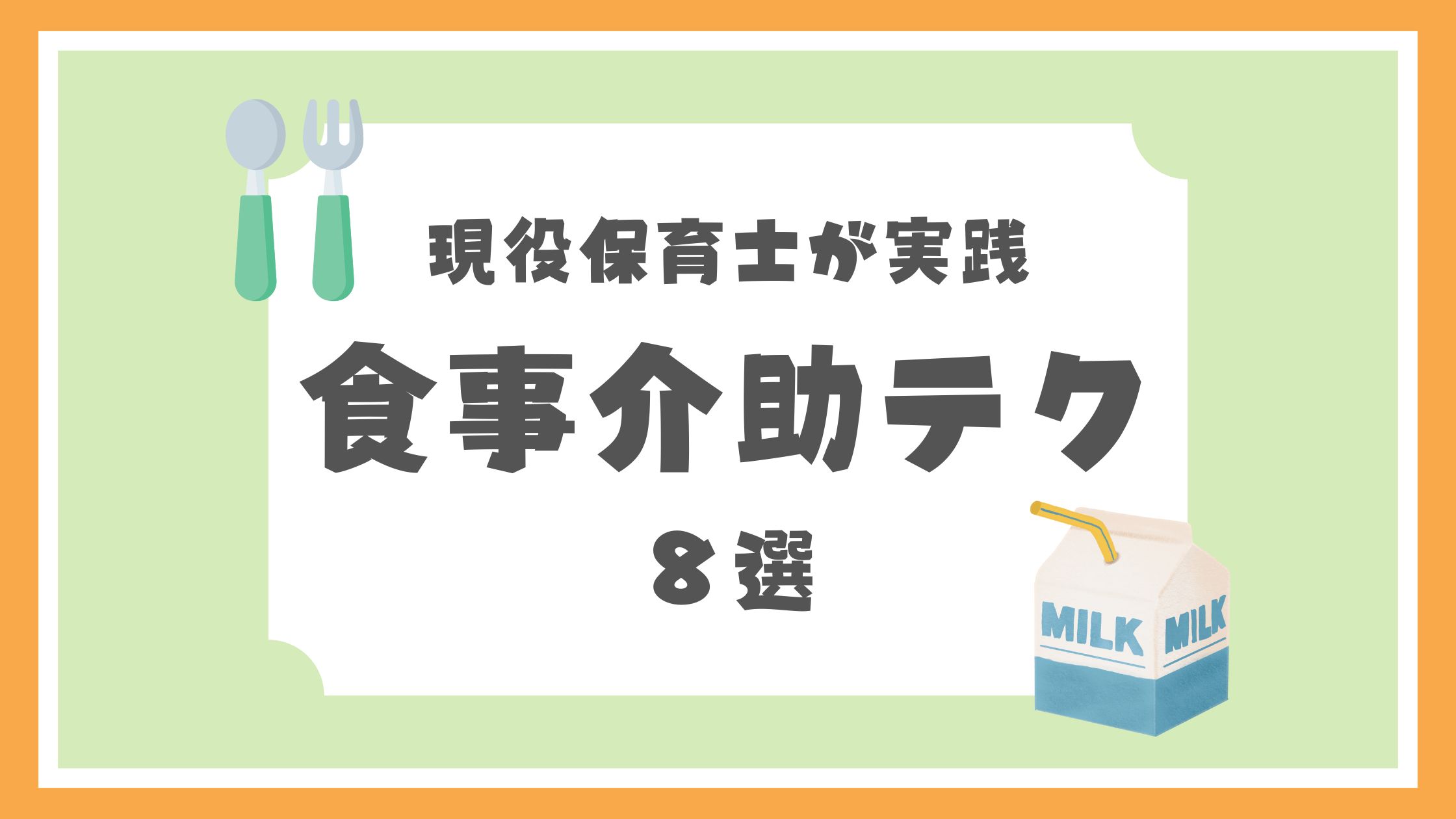

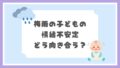
コメント